達成校目次 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 掲載されている学校名・校長名・PTA役員名と児童・生徒数は2009年3月末現在のものです。 |
★ 800万点達成校を訪ねました!
児童数は減っても県1位を独走岐阜県北方町北方小学校
|
|
岐阜県北方町立北方小学校(河合宣昌校長、520人)のベルマーク点数の累計が、運動参加から46年で800万点を突破しました。2位校を200万点以上引き離し、県内トップの大台到達です。

同小は、以前は児童数が千人近い大規模校で、ベルマークの集まりも良かったのですが、84年に北方西小、01年に北方南小が分離して児童数が減少し、ペースが鈍りました。700万点に到達するまで3〜4年毎に100万点ずつ上積みしていたのですが、700万点から800万点には8年近くかかりました。 それでも児童と学校、PTAが協力して、ベルマークの回収、整理に努めています。 児童は、毎月初めに配布される収集袋にベルマークを入れて学校に持ち寄ります。以前は中に入っている枚数を袋に書いていたのですが、競争をあおる恐れがあるとして、今は書いていません。ただし提出枚数が多い場合は、励みの意味で、普通は1個だけの受領スタンプを、10〜29枚は2個、30枚以上は3個押すことにしています。 
各学級には紙コップと牛乳パックを組み合わせた回収箱(主な番号とその他との計10種類に区分できる箱)があり、子どもたちは投入する段階で大まかに仕分けをします。 これらの回収箱を1カ所に集め、各学級に1人ずついるPTA厚生委員会(杉山理恵委員長、18人)のメンバーが隔月に出て細かく分類し、集計します。校区内のショッピングセンターや銀行支店などにもベルマーク箱を置かせてもらい、年に1、2回回収しています。 ベルマーク預金で、これまで一輪車や一輪車収納スタンド、ドッジボールなどを購入してきました。次はDVDプレーヤーを買う予定です。 
同小は09、10年度、文部科学省の「児童生徒の心に響く道徳教育推進授業」の指定を受けています。研究主題は「豊かに感じて判断し、仲間とともによりよくい起用とする児童の育成」。縦割り集団活動や保護者への道徳の体験授業などを通じて、豊かな心を持って、たくましく生き抜く力のある子どもの育成を図っています。 北方町は、弘法大師が創建したとされ、楼門や木造聖観音立像など4件の国指定重要文化財を所蔵する円鏡寺の門前町ですが、近年は岐阜市に隣接するベッドタウンとしても発展し、県内有数の人口密度を数えています。 《写真上から》 ・牛乳パックと紙コップを組み合わせて10のグループに分別できるように工夫したベルマーク回収箱。各学級に置いてあります ・仕分けや集計作業は隔月に1回、PTAの厚生委員が集まって取り組みます=以上は岐阜県北方町の北方小学校で ・学校北隣の円鏡寺は弘法大師の創建といい、楼門や聖観音立像など国指定4件をはじめ数々の重要文化財が残されています |
★ 800万点達成校を訪ねました!
自宅で点数整理、大阪初の800万点大阪府豊中市大池小学校
|
|
大阪府豊中市立大池小学校(横山賞三校長、715人)のベルマーク収集点数が8,00万点を超えました。1964年にベルマーク運動に参加して以来の累計で、800万点達成は府内初めてです。

ベルマークを担当するのはPTA施設委員会(戸川優子委員長ら14人)で、委員は希望者を募りますが、人気が高く毎年抽選になるようです。 収集・仕分け日は毎月第2水曜日。1週間ほど前に全児童に回収袋が配られ、児童は収集日までに持ち寄ります。収集日には職員室前に回収袋が置かれ、施設委員が回収して仕分けに入ります。 会社別に分けるだけで、それを分担して自宅に持ち帰り、点数別に分け、整理袋に入れます。自宅で仕分け整理した分は次回の収集・仕分け日に学校に持ち寄り、施設委員会役員に渡し、その後、その月の回収分を会社別に仕分けします。自宅整理分を受け取った役員は送り状に転記、最終集計し発送します。これを繰り返すことによってスムーズに作業が進められます。 今年度はインクカートリッジの回収に力を入れました。また学校以外でもスーパーや郵便局にも回収箱を置かせてもらっています。 
3月13日の仕分け日、戸川委員長や渡邉由美副委員長らが1年間の取り組みの感想を述べてくれました。 「すぐに子どもたちのためになる」「少し手間をかけると何倍、何十倍にもなって子どもたちに還元される」「意識するのとしないのと大違い。ベルマーク担当を順繰りにやってもらった方がよい」「素晴らしい活動だとわかった」。 大池小学校は阪急豊中駅すぐ側にあります。1936年創立で、現在「求めて学ぶ子どもの育成」を教育理念に掲げています。 《写真上から》 ・ベルマークの仕分けをするPTA施設委員ら ・感謝状を手に800万点達成を喜ぶPTA施設部長の戸川優子さん(右から3人目)、副委員長の渡邉由美さん(同4人目)ら施設委員のみなさん=豊中市の大池小学校で |
★ 700万点達成校を訪ねました!
保護者全員と児童、教職員が協力し700万点群馬県草津町立草津小学校
|
|
温泉観光地として有名な、群馬県草津町の草津小学校(黒岩幸恵校長、373人)が、ベルマークに参加30年で700万点を突破しました。群馬県ではダントツの1番で、年間10万点突破を目標に活動しています。
 同小は、1994年に300万点を達成し、それから7年で600万点を達成するというスピードで、あまりに集まるマークの量が多いために、全PTAへ整理をお願いするようになりました。「地域に格別な呼びかけをしなくても、無駄なく、無理なく、切り取るのが当然の事ように、習慣になっています」と埴田栄一教頭。その時期に教職員として同小に在籍していたそうです。 
具体的な活動は、児童のベルマーク委員が役場や公民館など5カ所に、掲示板やベル箱の設置、マークの回収をしています。集まったマークを毎月1回、委員会活動の時に会社別に仕分ける作業をします。全保護者は7、12、3月の年3回の作業日に担当者が振り分けられます。1回に集まる人数は60〜70人程度、学年ごとのテーブルに分かれて作業を行ないます。会社番号を書き込んだベニヤ板を使いマークを仕分け、折り紙で作った箱で点数別に分類し、数えていきます。作業に向けての下準備から送票作業まで扱うのは、学校事務局の山口幸美さん。「皆さんは手馴れたもの。改めて指示をしなくとも工夫しながら、能率よく進みます」と話す岩井美峰子さんは、1987年から20年間、担当事務局として関わっていました。2年前退職しましたが、毎回お手伝いに来て下さいます。 黒岩校長が毎週発行している学校便り「からまつ」には、作業風景の写真と一緒に集計点数結果から、折りたたみテントやスキー授業で使用するビブスなどの購入品のお知らせ、お礼の言葉が掲載されています。 草津町は、スキー複合で活躍した荻原健司・次晴兄弟の出身地としても有名で、校長室には卒業生である二人のサイン入り色紙が飾られ、「草津小のみんな、僕に続くようがんばってくれ!」と在校生を励ましています。 
同小の取り組みに、「スキー授業」や「読み聞かせ」など、10年以上続くボランティア活動があります。校庭には、ジャンプ台を備えたスキー場があり、3学期になると1年生からスキー授業を行います。アルペンやクロスカントリーのスキー技術向上に、たくさんのボランティアの方々が協力、子ども達も安全に楽しみながら上達するそうです。 《写真上から》 ・継続は力なり「さらに800万点を目指します」。中央は、感謝状を持つ学校事務局の山口さん、後列右側は埴田教頭です ・息も合い手際がよく、楽しげに作業する6学年のお母さん達。6年間の経験が違います ・ビブスは学年で色を変え、広いスキー場でも見分けが付きます。数え切れないお買い物。子ども達に喜ばれ、大切に使っています(草津小提供) =いずれも草津町立草津小学校で |
★ 700万点達成校を訪ねました!
近所のスポーツ店が強力援軍東京都文京区立窪町小学校
|
|
東京都文京区の窪町小学校(石井梅雄校長、661人)が700万点を達成しました。参加から45年、都内の参加約1900校・団体の中で、8番目の快挙です。

「窪町は 水辺の馬と 菊の花 善さを育む かやの大木」。石井校長が詠み込んだ3つのシンボルが教育活動の指導理念になっています。水辺の馬は「すすんで考えやりぬく子」。馬を水辺に連れて行くことはできても、無理やり水を飲ますことはできない、という故事にちなんでいます。菊の花は「よさを生かして共に生きる子」。たくさんの花びらが重なって一つの花になっていることから、力を合わせる大切さを説いています。実際に子どもたちは毎年栽培して湯島天神の菊花展に出品、金賞や銀賞に選ばれているそうです。かやの木は正門の横に大木があります。「今の木は2代目ですが、80年前の開校当初から大木があったようです」(石井校長)。たくましい元気な子を育てる、との思いが伝わります。 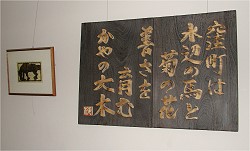
ベルマーク活動は「父母と先生の会」のベルマーク委員会(増井幸代委員長、19人)が受け持っています。収集日は年6回。1週間ほど前に、全校児童にそれぞれ回収袋を渡し、各クラスにあるポストに入れてもらう仕組みです。活動は主に土曜日の午前中。「土曜日なので、子どもたちもくるし、すごく楽しい雰囲気です。それに、勤めているお母さんが多いので、土曜日に活動するベルマーク委員会は人気が高いんですよ」と委員の一人、宮下良子さん。 増井委員長は「地域の応援も心強い味方です」と言う。とくに学校そばにある「大矢スポーツ」からは年2回ほどたくさんのマークが提供されるそうです。同小の周りは大学や付属の学校などがたくさんある文教地区。同スポーツには、ベルマーク協賛社ラッキーベルの上ばきや運動シューズを求めにくるお客さんも多い。でもベルマーク運動に参加していない学校も結構あるため、「箱はいらない」というお客さんからマーク付の箱を回収して貯めては、窪町小など近隣の3つの参加校に贈っているということです。ほかにも、封筒に入れて届けてくれる人もいるそうです。 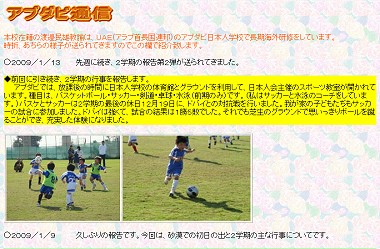
もう1つ、同小とベルマークの意外な?関係を見つけました。ホームページ http://www1.tcn-catv.ne.jp/kubomachi-ps/をのぞくと、「アブダビ通信」という珍しい項目があります。同校の渡邊民雄先生がUAE(アラブ首長国連邦)のアブダビ日本人学校で07年から海外研修中で、時おり届く報告が写真つきで紹介されています。砂漠の国の生活ぶりや食べ物の話など、なかなか楽しい内容です。実は、このアブダビ日本人学校にはベルマーク財団から外務省を通して過去3回の援助がされています。窪町小の活動も間接的につながっているのです。昨年は椅子と積み木が贈られました。どう使われているのでしょうか。今度はそのことも報告していただけるとうれしいんですが、渡邊先生。 《写真上から》 ・700万点の感謝状を持つ石井校長をはさんで、増井委員長(左)と宮下さん ・石井校長がシンボルを詠み込んだ句が校内に掲示されている =いずれも東京都文京区大塚の窪町小学校で ・アブダビ通信のページから |
★ 500万点達成校を訪ねました!
預金で約44万円の滑り台を購入金沢市大徳小学校
|
|
金沢市立大徳小学校(森多勉校長、803人)が、ベルマーク運動に参加以来40年の累計で、石川県内では7校目の500万点校になりました。03年11月に400万点校になってから5年余で100万点を上積みしました。

同小では毎月末、育友会(PTA)の厚生委員会(岩崎真由子委員長、26人)が担任の先生にベルマーク袋を渡し、子どもたちに配ってもらいます。子どもたちがベルマークを入れて返してきた袋は、先生がクラス毎にまとめて職員室前の箱に入れます。 これを厚生委員会が回収し、4月と8月を除く毎月第2金曜日に学校で仕分けをします。仕事をしているお母さんも多いため作業は午前の部(10時〜)と夜の部(6時半〜)に分け、都合のいい時間を選べるようにしています。集計は、担当する番号をくじで決め、自宅で行います。 
ベルマーク集めでは地域の協力も仰ぎ、郵便局やスーパーなどに回収箱を置かせてもらっています。 同小はこれまで、その年に集めたベルマーク預金はその年に使うというような方式で、定期的にお買い物をしていました。しかし、4年前に赴任した森多校長が「もっと大きなお買い物を」と提案したのを受け、4年間はお買い物を控えました。久しぶりのお買い物は08年秋で、滑り台を購入しました。05〜06年度の3年間に集めた約48万点をほぼ使い切る約44万円のお買い物でした。 03年に県庁が近くに移転してきたこともあって同小の校区では人口が急増しており、森多校長が赴任してからの4年間で児童数が約100人増えました。  09年度はさらに60余人増え、市内の小学校で2番目の規模です。そのため教室の確保が大変で、特別教室を普通教室にしたり、ランチルームを算数の少人数教室に充てたりしています。また昇降口の下足箱の追加や教職員用駐車場の確保なども難題です。
09年度はさらに60余人増え、市内の小学校で2番目の規模です。そのため教室の確保が大変で、特別教室を普通教室にしたり、ランチルームを算数の少人数教室に充てたりしています。また昇降口の下足箱の追加や教職員用駐車場の確保なども難題です。同小は隣接の木曳野小、大徳中と英語の一貫教育に取り組むなど、小中一貫教育を試みています。最近は「聞く」「話す」の国語力向上の研究や、子どもたちが履物の整理やあいさつなど、当たり前のことを当たり前にできるようにする教育に力を入れています。 《写真上から》 ・子どもたちが持ち寄ったベルマークを袋から取り出し、番号別に仕分けします ・財団からの感謝状を囲む育友会厚生委員のお母さん方 ・08年度のお買い物は滑り台。子どもたちは大喜びでした=いずれも金沢市の大徳小学校で |
★ 500万点達成校を訪ねました!
ノーベル賞朝永さんの母校が500万点京都市錦林小学校
|
|
京都府京都市立錦林小学校(伊藤進校長、447人)のベルマーク収集点数が500万点を超えました。1962年にベルマーク運動に参加して以来の累計です。500万点達成は府内11校目です。

ベルマークはPTA設備助成部(長尾めぐみ部長ら14人)が担当します。回収箱は学年に1個づつ廊下に置いています。毎月17日を収集日にしていますが、いつでも入れることができます。学校正門には回収ボックスをおき地域の人らの協力を仰いでいます。 仕分けは2ヶ月に1回ぐらい。部員のほかに仕分けボランティアを募り、毎回7、8人が参加しています。学校では会社別に仕分け、点数別仕分けは昼の作業に参加できなかった部員に自宅でしてもらいます。最終集計、発送は前期後期の各1回。 昨年秋には、近くの銀行支店からベルマークの寄贈がありました。 
錦林小学校は明治2(1869)年開校の歴史を誇ります。著名な卒業生も多く、中でも有名なのが1918年(大正7年)卒業のノーベル物理学賞受賞の朝永振一郎博士と1917年卒のフランス文学者の桑原武夫さん。玄関ホールには両氏を顕彰するコーナーがあります。朝永さんの「科学する子」「科学精神」の色紙、ノーベル賞受賞後に母校を訪問した写真、桑原さんの写真や著作などが飾られています。 錦林小は「自分のおもいや考えを豊かに表現できる子ども」を研究テーマに国語教育に力を入れています。昨年11月に行われた研究発表には17府県の教育関係者が参加しました。 《写真上から》 ・今年度最後の仕分け作業をする錦林小学校PTA設備助成部員ら ・ノーベル物理学受賞朝永振一郎博士とフランス文学者桑原武夫を顕彰するコーナー=いずれも京都市の錦林小学校で |
★ 400万点達成校を訪ねました!
どっさり届くマヨネーズ袋でスピード達成茨城県下妻市下妻小友幼稚園
|
|
茨城県下妻市は、県の南西部にある人口約4万5千人の田園都市です。養豚や梨づくりが盛んで、県内有数の米どころでもあります。

関東鉄道下妻駅から徒歩3分ほどにある下妻小友(しょうとも)幼稚園は、昭和2年(1927年)創立で80年余りの歴史があります。200人近い園児がいたこともありますが、少子化に伴い数が減り、いまは56人(3月)です。 このたび、1969年にベルマーク参加以来の累計が400万点に達しました。300万点になったのが04年9月です。少人数なのに、わずか4年半で100万点を積み上げたのには、わけがありました。 市内にお好み焼きを作る工場があります。製品に添えるキユーピーマヨネーズの小袋は、40個ずつビニール袋に入って納められます。小袋を取り出した大量の空き袋には、それぞれ5点のベルマークがついています。4年ほど前から、その空き袋がまとめて同園に届くようになりました。それに、園児や卒園生の家から届くベルマークが加わって、スピード達成できたのです。 
キリスト教の精神を基にしたこの幼稚園には、独特の教育方針が掲げられていますが、「ベルマークの整理」もその一つです。年長組の園児たちが、月に一度、最初の仕分けをします。その作業を通じて、整理や分類などの方法を身につけます。卒園前には「後輩」たちに教えて引き継ぐのだそうです。「(作業を)見ていて、こどもの成長を実感しました」というお母さんもいました。 その後の作業はお母さんたちの出番ですが、大量のビニール袋からのマーク切り取り、という大仕事が加わります。ビニール袋はやわらかいので、切り取るのがやっかいでした。一人のお母さんが、ボール紙の台紙に長さ5cmほどの鋲(びょう)を2本刺した、特殊用具を考えつきました。 その台にビニール袋を1枚ずつそろえて刺します。10枚刺したら、マークのわきをホチキスで止めて切り取ります。これで作業が格段にスピードアップしました。とはいえ大量なので、月に1度の作業は9時から始めて午前中いっぱいかかります。お母さんたちには3月ごとに当番が回りますが「手作業の間は、会話しながらなので楽しいですよ」。 
これまでに全自動式のピアノやトランポリン、温蔵庫などを購入しました。昨年は木琴や太鼓のスタンドを更新しました。教頭の浅野道子先生は「次はできれば古くなった遊具を取り替えたいですね」と話していました。 園の教育方針の柱は「あそびを中心とした保育」です。年長、年中、年少の3クラスが一緒になって「開戦ドン」と子どもたちが名づけた陣取りゲームや「バトンタッチ」(リレー)などで遊びます。秋の泥ダンゴづくりも人気があるそうです。浅野先生は「毎年クリスマスに卒業生を招待するのですが、懐かしがって一緒に夢中で遊んでいますよ」。 訪ねたのは3月で、年長組がお母さんたちと卒園の記念にユーカリの木を植樹をしていました。この子どもたちも、今年のクリスマスには先輩たちとともにお呼ばれして、「開戦ドン」や「バトンタッチ」に興ずるのでしょう。 《写真》 ・記念植樹をする年長組の園児とお母さんたち ・記念植樹のあと、残ったお母さんたちにビニール袋からのマーク切り取り作業を見せてもらいました。正面が福西園長、右隣が浅野教頭 ・台紙の2本の鋲に、ビニール袋をそろえて10枚刺して1セットでき上がり=いずれも下妻小友幼稚園で |
★ 400万点達成校を訪ねました!
フェスティバルでベルマーク集め横浜市葛野小学校
|
|
横浜市泉区にある葛野小学校(石井治校長、536人)が400万点を達成しました。参加して33年、毎年秋に開かれる葛野フェスティバルでベルマークを集めています。

フェスティバルは、秋の文化祭にあたり、生活科や総合的な学習で勉強したことを発表するもので2002年から始まりました。1、2年の低学年こそ折り紙を作ったり、ゲームをしたりしますが、5年は環境をテーマにゴミや水、4年生は福祉をテーマにして点字を取り上げたりします。展示だけでなく紙芝居形式や、寸劇でアピールすることもあるそうです。 ベルマークや古切手などが入場券代わりになります。昨年は地域の方も含めて800人以上が訪れ、古切手9648枚、書き損じ葉書141枚、市営地下鉄の交通カード4382枚、が集まり、ボランティア団体などに贈られました。一緒に集まった鉛筆213本、ノートなどは、ベルマーク運動とも関係がある財団法人ジョイセフ(家族計画国際協力財団)に贈られたそうです。 
フェスティバルで集まったベルマークは約3万5000点。これ以外には収集しておらず、PTA文化厚生委員会24人が仕分けから集票、発送まで行います。訪れた日は発送が終わっていましたが、これまで残ったマークを集まった4人が仕分けました。「小さなマークや、マークの周りに枠がないのはわかりにくいですね」。「お砂糖が入っていたマークは手がべたべたして大変」。文化厚生委員会は講師を招いての講習会も担当するなどの仕事もあり、人集めが大変で、自宅へ持ち帰っての作業になることも。幼稚園でも活動歴のある委員長の合田優子さんは「でも文句言いつつ、おしゃべり出来るのが楽しみ。余り知らなかった方ともコミュニケーションがとれますし」と話していました。 
お買い物では、最近は折り畳みテーブル、一輪車、テントなどを購入していますが、参加間もない1981年にはグランドピアノを購入したのが自慢。体育館のステージにあり3月18日にあった卒業式でも活躍しました。 同小は横浜市営地下鉄中田駅から歩いて15分足らずの住宅街にあり、1975年に中田小、汲沢小から分かれて開校しました。「未来を拓く健やかな葛野の子」が教育目標で、週3回10分間の朝読書を推進、ボランティアによる読み聞かせも毎月行われています。 《写真上から》 ・おしゃべりしながら手は休まず。仕分け作業をするPTAと文化厚生委員会のみなさん ・感謝状を持つ合田委員長、右は伊波洋美副委員長。上列右から市川清洋副校長、石井校長、贄田都子PTA副会長、小貫庸子書記 ・葛野フェスティバルでの受付の様子(葛野小学校提供)=いずれも横浜市葛野小学校で |
★ 400万点達成校を訪ねました!
1年生保護者の有志が整理・集計を手助け岐阜県大垣市西小学校
|
|
岐阜県大垣市立西小学校(名和茂樹校長、588人)のベルマーク点数が、1961年の運動参加以来の累計で400万点を突破しました。県内で9校目、市内では4校目です。

同小のPTAでベルマークを担当するのは総務委員会(大島美江委員長、9人)です。年度初めに全保護者に文書でベルマークの意義を伝え、回収への協力を呼びかけます。また校区内の銀行とスーパーマーケットに回収箱を置かせてもらって、適宜、委員が回収しています。 同小は、原則として毎月15日を「ベルマークの日」にしています。子どもたちが専用の袋にベルマークを入れて学校に持参する日です。これを総務委員が毎月、番号別に仕分けします。6、9、11、2月の年に4回は、総務委員のほか1年生の保護者の有志が出て、整理、集計作業に取り組みます。毎回、20余人が集まるそうです。 ベル預金では、ある程度金額が積み上がったところでお買い物をする方針で、これまでは新1年生のクラスに鉛筆削りをそろえるなどしてきました。 
同小は伝統的にPTAや同窓会の活動が盛んで、相撲大会やお正月遊びなど、学校と連携した行事をたくさん実施しています。校庭の一角にある屋根付きの相撲場は、同窓会が寄贈してくれたものです。 大垣市は水の都として知られ、芭蕉の「奥の細道」の結びの地としても有名です。そこで「ふるさと教育」に力を入れています。代表的な活動は15年前から続く「舟下り」で、6年生が舟に乗って水門川を下り、俳句作りなどに取り組んでいます。 近年は外国人の児童が増え、30人ほどが学んでいることから、国際理解教育も推進しています。日本人と外国人が一緒に学習できる環境作りを大切に考えるもので、外国人の児童に大垣市を知ってもらうことにも努めています。 《写真上から》 ・財団からの感謝状を囲んで、前列右から08年度総務委員長・大島美江さん、09年度委員長・大橋繭香さん、同副委員長・青木由香里さん。後列は09年度PTA会長・若園比呂志さん(右)と名和校長 ・子どもたちが持参したベルマークは毎月PTA総務委員が整理し、番号別の仕分け箱に入れます=いずれも大垣市立西小学校で |
★ 400万点達成校を訪ねました!
念願の黒板消しクリーナーを学年に1台注文大阪府堺市立新金岡小学校
|
|
大阪府堺市立新金岡小学校(村田博美校長、544人)のベルマーク収集点数が400万点を超えました。1967年にベルマーク運動に参加して以来の累計です。400万点達成は府内32校目。
PTA施設委員会(大平美樹委員長ら18人)が担当します。学級委員が選ばれますが、08年度で仕事を持っている人が半分ほど。 
収集・仕分け日は毎月1日。クラス担任が児童から回収袋を受け取り、職員室前の箱に。PTA施設委員はこれを集め、仕事のある人と学校で作業できる人に会社ごとに分配。仕事のある人は自宅で会社別、点数別に分けて次回の収集・仕分け日に持ち寄ります。 持ち寄ったベルマークは役員が最終集計します。委員は仕分けしたベルマークを渡した後、この月収集した分を受け取り、仕分け作業に入ります。これを繰り返す形になります。発送は学期に1回です。 ここ数年、買い物を控え、今年、念願の黒板消しクリーナーを学年に1台、計6台を注文しました。学校側は心待ちしています。 山崎美恵子副委員長は「今年度は(黒板消しクリーナーという)形が出来良かったです」と話していました。 《写真》 ・感謝状を手に400万点達成を喜ぶPTAの山崎美恵子副委員長(前列右から2番目)ら施設委員ら=堺市の新金岡小学校で |
★ 400万点達成校を訪ねました!
自宅で、会社ごと点数ごとに仕分け大阪府四条畷市くすのき小学校
|
|
大阪府四条畷(しじょうなわて)市立くすのき小学校(竹内千佳夫校長、552人)のベルマーク収集点数が400万点を超えました。1971年にベルマーク運動に参加して以来の累計で、400万点達成は府内33校目です。

ベルマークを担当しているのはPTA環境保健委員会(堀井由美子委員長ら18人)で委員は各クラスから選ばれます。クラスに回収箱を置いてあり、年2回(7、12月)、委員は自分のクラスの分を自宅で、会社ごと点数ごとに仕分けします。仕分けしたベルマークを1、2週間後に学校に持ち寄り最終集計します。発送はインクカートリッジの点数証明書が届いてからします。 回収箱は児童のほか、公民館、スーパー、薬局などにも置かせてもらっています。学校の玄関にも回収箱を置いています。 くすのき小学校は北出小と四条畷西小が統合して2006年に開校しました。その新校歌「あかるい声とあかるい笑顔」を作詞作曲したのが四条畷西小出身のタレント、山口智充さんです。山口さんは「ぐっさん」の愛称で親しまれており、ミュージシャン志望だっただけに音楽の才能が高いことなどから白羽の矢がたちました。 「青い空に翔くような 広い心を持とう 生きてることを喜びながら 何でも楽しもう 大きな夢もって 前だけを向いて歩こう いつもあかるい笑顔あふれる くすのき小学校」 山口さんは学校関係者に「1年から6年まで歌えるような歌作りは難しかった」と語っていたそうですが、明るく親しみやすい校歌になっています。 くすのき小学校は「基礎学力の定着」を掲げ、朝の会の読書、毎週1回の算数タイムでスキルアップを図っています。 《写真》 ・作詞作曲した「ぐっさん」山口智充さんから贈られた新校歌の額を前に竹内千佳夫校長(左)、PTAの堀井由美子環境保健委員長(中)、川上由紀副委員長(右)=大阪府四条畷市のくすのき小学校で |
★ 400万点達成校を訪ねました!
在宅含めボランティア40人で仕分け兵庫県西宮市立小松小学校
|
|
兵庫県西宮市立小松小学校(和田美津代校長、821人)のベルマーク収集点数が400万点を超えました。1962年にベルマーク運動に参加して以来の累計です。

ベルマークを担当するのはPTAの冨万裕美さんを中心にしたボランテイアグループ。ボランティアは年度初めに募集、08年度は学校にきてくれる人と在宅で協力する人の合わせ40人ほど。児童は大きいペットボトルで作ったクラスの回収箱にいれます。児童以外では校区内のスーパーストアなどに回収箱を置かせてもらっています。 1学期に1回、仕分け。学校に来るボランティアが会社ごとに仕分けし、あとは在宅ボランティアに点数別の仕分け集計を、お願いします。在宅分が戻ってきたら、冨さんらリーダーらが発送します。 これまでに逆上がり補助機、一輪車の置き台などを買いました。 ボランテイア方式は5年前から。それまでPTA保健愛護部が担当していましたが、小学生が被害を受ける事件、事故が相次いだことから安全面だけを担当し、ベルマークを切り離しました。5年続いたボランテイアですが、新年度からPTA学年部が中心になる予定です。 《写真》 ・ベルマークボランティアを発足当初から活動を続けてきた冨万裕美さん(左)、山下美由紀さん(中)、児玉千佳さん(右)=西宮市の小松小学校で |
★ 400万点達成校を訪ねました!
自宅で仕分け・集計し全体作業は学期1回大分県佐伯市渡町台小学校
|
|
大分県佐伯市立渡町台(とまちだい)小学校(分藤高嗣校長、691人)が参加30年で累計点数400万点を達成しました。県内21校目です。

活動は、PTAベルマーク委員会(二宮たつ江委員長)が担当し、各クラスから1人の計24人がメンバーです。 毎月1回、児童に回収袋を配り、集まったマークは、そのクラスの委員が自宅で仕分け・集計します。各学期に1回、委員全員が学校のサポータールームに集まり、全体集計を行います。 08年度最後の全体集計作業は、いつも通り午前9時半から始まりました。仕事を持っているお母さんも多いとのことですが、年3回の作業なので勤務先との都合がつけやすいそうです。この日も出席は22人、ほぼ全員がそろいました。会社別の発泡スチロール製トレーに、持ち寄ったマークを集め、点数別に10枚ごとにテープを張っていきます。みんな丁寧にマークを切りそろえています。「大変でしょう。そんなに手間をかけなくてもいいんですよ」と声をかけると、「きちんとしているほうが、財団で点検されるときにやりやすいでしょう」と、ありがたい言葉が返ってきました。 佐伯市は05年3月に、旧佐伯市と南海部郡の5町3村が合併し、新たにスタートしました。面積は約903平方キロメートルで東京都のほぼ四分の一にあたり、市町村では九州で最大です。渡町台小は、旧佐伯市中心部の住宅街にあり、児童数は市内の小学校で最多です。 《写真》 ・08年度最後の全体作業には、ほぼ全員のベルマーク委員が参加、点数別のマークを10枚ごとにテープを張っていきます =大分県佐伯市の渡町台小学校で |
★ 300万点達成校を訪ねました!
園児の祖父母が「ダブル」で収集協力福島県田村市わかくさ幼稚園
|
|
通園バスが到着するたび「おはよーございます」と元気なあいさつが聞こえてきます。福島県田村市にある、若草学園わかくさ幼稚園(牧公介園長、341人)が、ベルマーク運動に参加して25年で300万点を達成しました。2008年度の集計点数は、12万点以上集めて、県内で12番目になりました。

1956年、船引キリスト教会内に「おさなご学園」として創設し、1974年、若草学園わかくさ幼稚園となってから、今年の4月で35年を迎えます。1万4481平方メートルという広い園内で、3歳から5歳までの園児がのびのびと動き回っています。 ベルマーク活動は、PTAベルマーク委員会(田村美香委員長、52人)が行っています。4月と8月を除いた月の、第3木曜日に幼稚園会議室に集まり、会社別に仕分ける作業だけを行い、各会社別の大きなビニール袋にまとめておきます。ベルマークを財団に発送する9月と2月の年2回は、会社ごとに点数計算をして発送します。最近増えてきたのがインクカートリッジです。「個数証明はがき」を一緒に発送できるように、前もって整理しています。 
ベルマーク便りは、年2回の集計点数を報告するほか、新参加協賛会社の商品紹介や無効になる会社名など、動きがある時は随時お知らせをしています。 錢高美和PTA副会長は、「当園の強みは、園児の両親それぞれのおじいちゃんおばあちゃんがダブルで収集に協力してくれること。運動会などは、孫の成長を楽しみに集まるギャラリーでいっぱいです」と話します。6年間ベルマーク活動に関わったベテランで、古いマークのことなどにも詳しく、頼もしい存在でした。田村委員長は「1点でも無駄にならないように役立てたいと思うようになりました」と話していました。 
ベルマークでお買い物した中で、移動式鉄棒やノンスリップカラーマットなどは「幼児体育」で活躍します。同園では、専門の指導教師による「幼児体育」や、外国語と外国人に親しむため「英語レッスン」を取り入れています。「未来を見つめる教育」として外国人教師の指導で効果をあげ、こどもたちの楽しみになっているそうです。 《写真上から》 ・ベルマーク委員が力を合わせ300万点になりました。牧園長(左側)と感謝状を持つ田村委員長。後列中央には錢高PTA副会長です ・話も弾む仕分け作業、使い終わったトレーや牛乳パックで会社別に分けていきます ・お買い物した移動式鉄棒とカラーマットで楽しげに遊ぶ園児達。「幼児体育」の成果が伺えます(学園提供)=福島県田村市若草学園わかくさ幼稚園で |
★ 300万点達成校を訪ねました!
お買い物の横断幕、陸上大会などで活躍埼玉県草加市立新田小学校
|
|
埼玉県草加市の新田(しんでん)小学校(片岡敬一校長、709人)が、300万点を達成しました。県内では111校目です。「111の数字は語呂が好いですね。2008年度、創立135周年を迎えた年に、達成の感謝状をいただき、校長として新田小に着任できた事は幸せです」と片岡校長は、にこやかに話していました。

ベルマーク運動に参加して40年、クラスから2人選出のPTA学級委員40人が活動しています。まとめ役は、3年生の学級委員(日野由美学年長、6人)です。各教室にベルマーク箱を置き、集まったマークは、学年ごとに学級委員が自宅で会社別に仕分けます。分類がされた6学年のマークを集めて、点数明細を数えるのは、3年学級委員メンバーです。年5回のPTA理事会の後、学校で集計作業しています。「もう少し人数が増えるとよいと思うのですが」と日野学年長。整理、集計作業の大変さが改善されれば、と願っていました。 
ベルマークのお買い物で、10年前に横断幕を購入しました。「ベストをつくせ!!新田小」と文字入れされ、陸上大会など数々の大会で使われていますが、どこにいてもとても目に付きやすく、便利だそうです。そのほか、本やソフトバレーセットなど数多くの備品も購入、皆さんから喜ばれています。 同小では、毎週木曜日の朝30分間、読書タイムで読み聞かせや「全校音朗読会」を実施しており、充実した図書室も自慢です。また行間休み時間には、23人の保護者ボランティアによる「エルマーお話会」があります。「エルマー」とは絵本「エルマーの冒険」からとり、"子どもと一緒に絵本の世界を冒険しよう"と月2回、大型の手作り本やパネルシアターを使って活動しています。この他、地域の方の協力で全学年読み聞かせもあります。読み聞かせは、本に親しみやくなり、子ども達も楽しみにしているそうです。 
草加市は、相撲が盛んなところで、市内の小学校の中で1番早く土俵が造られた学校です。相撲教室があり、参加者は30人ほどで、女の子も負けずに頑張っているそうです。こうしたことは、朝日小学生新聞の「学校さんぽ」コーナーに今年の1月、「礼儀を大切にし、たくましい心と体が育っています」という体育主任後藤利宏先生の言葉とともに、掲載されました。 《写真上から》 ・PTA学年委員のみなさん1年間ご苦労様でした。片岡校長(左端)と300万点の感謝状を持つ日野学年長 ・陸上選手権大会でも活躍、横断幕は新田小の顔となっています(新田小学校提供) ・「エルマーお話会」の方のお話を、熱心に聞き入る子ども達(同小提供)=草加市立新田小学校で |
★ 300万点達成校を訪ねました!
めざすは赤外線暖房機の購入横浜市六つ川小学校
|
|
横浜市南区の六つ川小学校(松元博志校長、557人)が、300万点の大台を突破しました。ベルマーク運動に参加して42年。
 2004年度はソーラー花時計や会議用テーブルなどを購入し、2007年度から「赤外線暖房機ブライトヒーター」と「学校向け安全セット」の購入に向けてベルマーク収集に励んでいます。
2004年度はソーラー花時計や会議用テーブルなどを購入し、2007年度から「赤外線暖房機ブライトヒーター」と「学校向け安全セット」の購入に向けてベルマーク収集に励んでいます。
活動を支えるのは、PTAベルマーク委員会(代表小池一樹さんと佐々木直子さん、18人)です。各教室にベルマーク回収箱を設置し、毎月1回、ベルマークの活動日に集めています。7月、12月、2月の年3回、仕分けから点数計算などの収集活動を重ねてきて、2008年度には、希望の赤外線暖房機ブライトヒーターを購入できる計画でした。ところが、後期「お買いものガイド」を見ると、価格が値上がりしていました。  「08年度の収集点数を合わせて、注文できるはずでしたがかないませんでした」と、佐々木さんは肩を落としていました。小池さんは「季節商品ですから、2009年は早めに準備するようにします」と話していました。
「08年度の収集点数を合わせて、注文できるはずでしたがかないませんでした」と、佐々木さんは肩を落としていました。小池さんは「季節商品ですから、2009年は早めに準備するようにします」と話していました。
呼びかけは、年4回の「ベルマーク委員会だより」を発行してお知らせするほか、学区内の郵便局と生協のお店にベル箱を設置して、地域から協力をいただきます。 同小では、地域の方々や保護者の協力が盛んで、「六つ小おやじの会」メンバーの活躍も目立ちます。毎年10月に行う「六つ川小フェスティバル」や餅つき大会などに向けて、出し物などの打ち合わせから準備まで、とても熱心な様子がホームページから見ることができます。 小学校は高台にあり、傾斜地に作った畑を利用した野菜栽培活動が特色です。  「畑を活用した栽培活動と、以前に全国花いっぱいコンクールで最優秀賞を受賞したことは自慢です」と松元校長。畑で栽培した野菜は大根やジャガイモ、ブロッコリー、スイカなど16種類以上、収穫の喜びや作り上げる苦労を体験しています。昨年、収穫した大根は60本以上、給食の煮物やサラダなどに調理されました。「リサイクル」の取り組みでも、環境委員会の子ども達が中心になって空き缶回収を行っており、横浜市立小学校の中で回収率が1番になり、リサイクル協会から表彰され、収益金は学校の園芸活動に使いました。さらに、給食調理で出る野菜の切りくずなどを、コンポストで肥料にして畑に使っているそうです。
「畑を活用した栽培活動と、以前に全国花いっぱいコンクールで最優秀賞を受賞したことは自慢です」と松元校長。畑で栽培した野菜は大根やジャガイモ、ブロッコリー、スイカなど16種類以上、収穫の喜びや作り上げる苦労を体験しています。昨年、収穫した大根は60本以上、給食の煮物やサラダなどに調理されました。「リサイクル」の取り組みでも、環境委員会の子ども達が中心になって空き缶回収を行っており、横浜市立小学校の中で回収率が1番になり、リサイクル協会から表彰され、収益金は学校の園芸活動に使いました。さらに、給食調理で出る野菜の切りくずなどを、コンポストで肥料にして畑に使っているそうです。
《写真上から》 ・前列、松元校長と武井由美子PTA会長、後列左から委員会代表の佐々木さん、PTA書記の坂本明子さん、委員会代表の小池さん、濱田哲也副校長 ・おしゃべりしながら和やかに仕分け作業が行われます。目の前にある「ベル箱」は、各教室のドアに掛けてあり、紐を外せば持ち運びが簡単で回収にも便利です(六つ川小学校提供) ・「六つ小おやじの会」の協力で行う餅つき大会は、子ども達に人気、楽しみの一つです(同小提供)=いずれも横浜市立六つ川小学校で |
★ 300万点達成校を訪ねました!
最終集計にはボランティアも参加滋賀県草津市草津第二小学校
|
|
滋賀県草津市立草津第二小学校(稲垣保善校長、747人)のベルマーク収集点数が300万点を超えました。1973年にベルマーク運動に参加して以来の累計で、300万点達成は県内30校目です。

PTA研修部(高橋美代子部長ら22人)が担当します。委員はクラスから1人選ばれます。 収集仕分けは学期に1回。児童が持ち寄ったベルマークを担任が職員室前の回収箱に。仕分けは回収して3日後ぐらいにします。1学期は5,6年生の委員、2学期は3,4年生の委員、3学期は1,2年生の委員と分けています。担当の委員は3、4回かけて会社、点数ごとに仕分けします。 最終集計は、一般募集のボランティアが参加しており、これをベルマークサロンと呼んでいます。作業そのものは1時間ほどで済み、後の1時間は茶話会になります。発送は役員がします。 草津第二小は学力、体力向上に力を入れています。 《写真》 職員室前のベルマーク回収かごの前に立つPTA研修部長の高橋美代子さん=草津市の草津第二小学校で ◇ ※ 掲載されている学校名・校長名・PTA役員名と児童・生徒数は2009年3月末現在のものです。 |