�B���Z�ڎ� |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�� 600���_�B���Z��K�˂܂����I
�S�Z�����������������Q�ʍZ���x�R�s�ʼn����w�Z
|
|
�@�S���w�Z�������������ĂQ�O�O�W�N�x�ɔ��������x�R�s���ʼn����w�Z�i�|������q�Z���A�S�U�O�l�j�̃x���}�[�N���[�_�����A�v�łU�O�O���_�ɂȂ�܂����B���ꂼ��̊w�Z���ςݏグ�Ă����_�������Z���ꂽ���ʂŁA����s�̊��쒆�w�Z�Ɏ��������Q�Ԗڂɖ��o�܂����B

�@�����́A�h�[�i�c�����ۂŎ��������������Ă���s���S���̏��w�Z�X�Z���R�Z�ɂ���Ƃ������s�̑�_�ȓ�����ɂ���Ēa�����܂����B�܂�05�N�x�ɑ��ȗցi��������j���Ɣ��l�������������A�O�U�N�x�Ɉ��쉮���A�O�W�N�x�ɂ͈��������������܂����B����ɍ��킹�ʼn����w�Z�̕~�n�ɁA�����ƈ�̉������ŐV�s�̍Z�ɂ����݂���܂����B �@���������S���̂����A���l���������̓x���}�[�N�^���ɎQ�����Ă��܂���ł������A���͈��쉮���ƈ��������P�X�U�P�N�A���ȗ֏����U�Q�N�ɎQ�����A���ꂼ�ꒅ���Ɋ����𑱂��Ă��܂����B��������܂łɈ��������R�O�O���_�ɓ��B���Ă����̂��͂��߁A���쉮���͖�P�U�R���_�A���ȗ֏��͖�P�R�S���_���W�߂Ă��܂����B �@�O�T�N�x���瓝�����i�ޒ��Ńx���}�[�N�����͈ꎞ�x�~�̏�Ԃł������A�O�W�N�t�A�ł������Ɋ������Ă������������������Ă������ƂŁA�V�������g�݂��{�i�����܂����B�w�N���Ƃ̎d�������Ȃǂ͈������Ŏg���Ă������̂������p���A���W�̃m�E�n�E���������ł̕�����傢�ɎQ�l�ɂ��܂����B 
�@���g�݂̒��S�́A�o�s�`�̉�����C�ψ���i����z�q�ψ����A�P�U�l�j�ł��B�N�ɂX���̃x���}�[�N���̑O�ɁA�e�N���X�S���̈ψ����S�C�̐搶�Ƀx���}�[�N�܂�n���A�q�ǂ������ɔz���Ă��炢�܂��B�����ɁA�e���S���̈ψ����Z���Z���^�[�i�E�����j�Ƀx���}�[�N�d���������^�сA�搶�Ɋw�N���Ƃɒ�߂��ꏊ�ɉ^��ł��炢�܂��B �@�q�ǂ������͉Ƃ��玝���Ă����x���}�[�N��ԍ��ʂɎd�����Ĕ��ɓ���A����I�������x���}�[�N�܂Ɏ����ł��ق��уV�[�����Đ搶�ɒ�o�A�搶�͑܂��܂Ƃ߂ĉ�����C�ψ��ɕԂ��܂��B�x���}�[�N�̓������d�������͐搶���Z���Z���^�[�ɖ߂��A�����������C�ψ����o�s�`��ɉ^�т܂��B�q�ǂ���������܂��Ɏd�������Ă��܂�����A���Ƃ͉�����C�ψ��������̒S������ԍ��̃x���}�[�N�����o���ĉƂɎ����A��A�W�v���܂��B �@������̐V�ʼn����Ƃ��ẮA�܂����������̂����Ă��܂��A����ψ����́u�����Ƀx���}�[�N�a���𑝂₵�A�w�Z�Ƒ��k���Ďq�ǂ������̖��ɗ����̂������v�Ƙb���Ă��܂����B �@�����̓��F�́A�Ȃ�Ƃ����Ă��a�V�ȐV�Z�ɂł��B�}��������`���[���A�R���s���[�^�[���Ȃǂ̋��p���𒆐S�ɁA���ɏ��w�Z�A���ɒ��w�Z��z���Ă���A�o���̒ʊw�H�ɂ��Ȃ�p�T�[�W���ƌĂԔ����O��Ԃ́A���J�̓��̗V�я�ɂ��Ȃ�܂��B���w�Z�̍Z��ɂ͓V�R�ł�~���A�K���X�������J����v�[�����ŏ�K�̂S�K�ɑ����܂����B���̍Z�ɂ��@���ɁA������ѓI�ȋ���Ɏ��g��ł��܂��B �s�ʐ^�ォ��t �E�x���}�[�N������o�s�`������C�ψ���̂��ꂳ����B�����p�b�N�ō�����d�������͓������ꂽ�������Ŏg���Ă������̂ł� �E�S���w�Z�������������Ēa�������ʼn����̕\���ցB���w�Z�Ƃ̈�̌^�Z�ɂ͍ŐV�̐ݔ����ւ��Ă��܂�����������x�R�s�̎ʼn����w�Z�� |
�� 500���_�B���Z��K�˂܂����I
�u���y�̊w�Z�v�x����w���̃s�A�m�������{���s�{����ꏬ�w�Z
|
|
�@�������{���s���{����ꏬ�w�Z�i�͊ۏ�v�Z���A�U�P�P�l�j���A�����ł͂U�Z�ڂɂT�O�O���_��˔j���܂����B
 �x���}�[�N�^���ɎQ�����ĂS�T�N�A�S�O�O���_����V�N�ŒB�����܂����B�Q�O�O�V�N�x�̏W�[���v�_�����P�S���_�ȏ�ŁA�����̃����L���O�͂T�ʂł����B
�x���}�[�N�^���ɎQ�����ĂS�T�N�A�S�O�O���_����V�N�ŒB�����܂����B�Q�O�O�V�N�x�̏W�[���v�_�����P�S���_�ȏ�ŁA�����̃����L���O�͂T�ʂł����B
�@�x���}�[�N�����𗦂���̂́A�o�s�`�̃x���}�[�N�ψ���i�O�ؗ���ψ����A�S�Q�l�j�ł��B������Ƃ͔N�U��A����Q�T�l���x�̎Q���҂Ŏd������ƂƏW�v�����݂ɍs���Ă��܂��B�c������Ђ̃}�[�N�́A�Q���o���Ȃ������l�ɂ��肢����ȂǁA�H�v���Ă��܂��B�J�[�g���b�W�̐����͎O�؈ψ����̒S���ł��B���ꂳ��B�����b�����e�݁A�ɂ��₩�ɍ�Ƃ���T�ŁA�P�l�فX�ƃJ�[�g���b�W�𐔂��Ă��邻���ł��B �@�n��̋��͂������A�����ق�X�[�p�[�ȂǂR�J���ɐݒu�̃{�b�N�X����͂�������̃}�[�N���W�܂�܂��B�O�W�N�x�̃x���}�[�N�ψ��́A������W�v�����߂Ă���l�������A�V���A�P�O���ɑ�������ł��A�܂��������}�[�N���c���Ă��܂��B  �u�c��}�[�N��S����������ƁA�P���ɂ͍��v�_���𑽂����āA�����ł���Ǝv���܂��v�Ɖ������q���ψ����B�P�������������ɑ���A�O�W�N�x���̏W�v�_���ɂȂ�Ɛ�������ƁA�u�l�����A������P�T�Ԉȏ㑁���J�[�g���b�W�����đ���A�t�����͂��悤�ɏ�������Ɨǂ���ł��ˁv�ƎO�؈ψ����͋���ł����B
�u�c��}�[�N��S����������ƁA�P���ɂ͍��v�_���𑽂����āA�����ł���Ǝv���܂��v�Ɖ������q���ψ����B�P�������������ɑ���A�O�W�N�x���̏W�v�_���ɂȂ�Ɛ�������ƁA�u�l�����A������P�T�Ԉȏ㑁���J�[�g���b�W�����đ���A�t�����͂��悤�ɏ�������Ɨǂ���ł��ˁv�ƎO�؈ψ����͋���ł����B�@���݁A�e��������}�[�N�̉���́A�����{�����e�B�A�ψ������`�������Ă��܂��B�o�s�`�̊F����́u�����ł��A�����Ȃǂ̍�ƂɎQ�����Ă��炦��Ƃ��肪�����v�Ƃ����v�]������܂����B �@�x���}�[�N�����ŁA�P�X�X�U�N�ɃO�����h�s�A�m�A�Q�O�O�S�N�ɂ͒��g�d�g���v�A�ܒi���˂Ȃǂ��w�����Ă��܂��B���͊g��R�s�[�@�̍w���Ɍ����Ċ撣���Ă��邻���ł��B  �@�u���͎q�ǂ������̉̐������������Ă��܂��B�������������������ł��v�ƒ��J��K�O�����B�����́u���y�̂���w�Z�v�����b�g�[�ɁA������}�[�`���O���̊����������ł��B�����͓��݃N���X�̎��������P��̑S�Z�W��Ŕ��\���Ă��܂��B�w���̃O�����h�s�A�m�́A�̈�ق̃X�e�[�W�ɒu���A��������ޏ�̉��t�Ŋ��Ă��܂��B �@�܂��A�}�[�`���O���́A����\���瓌�k��\�A�S�����Ɍv�W��o��Ƃ����P���������т�����܂��B�L���ɂ͓��k���ŁA�B�e�����ʐ^���W�����Ă���܂������A�����̃��j�t�H�[�����ƂĂ��f�G�ŁA�݂�Ȃ̐^���ȗl�q����͉��t����������悤�ł����B �s�ʐ^�ォ��t �E�o�s�`��c���ɂ͂���܂ł̊��ӏ厖�ɏ����Ă��܂����B�E����S�O�O���_�̊��ӏ�����M��a�q����A�T�O�O���_���ӏ�����O�؈ψ����A�R�O�O���_���ӏ�����������q���ψ����B��͒��J�싳���ł� �E���P��̑S�Z�W��Ɍ����āA�s�A�m���͂�ŗ��K����q�ǂ������̐��������܂��i�{����ꏬ�j �E�L���ɓW�����Ă��铌�k���̎ʐ^����́A�}�[�`���O���Ȃǂ́A��������̔M�S�ȗ��K���ʂ��f���܂����������{���s�̐{����ꏬ�w�Z�� |
�� 500���_�B���Z��K�˂܂����I
�����̃}�[�N�W�߂Őe�q���G�ꍇ�������s�䓌����w�Z
|
|
�@���W���߂��A�u���͂悤�������܂��v�ƌ��C�Ȃ������ŋ����ɓ����Ă��鎙���������A���ꂳ�����Ί�Ō}���܂��B�����h�Z������x���}�[�N�܂����o���Ă��ꂳ��ɓn���ƁA�u��������W�߂Ă��ꂽ�̂ˁB���肪�Ƃ��v�Ɛ����Ԃ��Ă��āA�����͂ɂ�����B
 �T�O�O���_��B�����������s�䓌��̐��w�Z�i��c���Z���A�S�O�R�l�j�ł́A�}�[�N���W�߂閈����P���j���̒��A�e�����Őe�Ǝq�̐G�ꍇ���������܂��B
�T�O�O���_��B�����������s�䓌��̐��w�Z�i��c���Z���A�S�O�R�l�j�ł́A�}�[�N���W�߂閈����P���j���̒��A�e�����Őe�Ǝq�̐G�ꍇ���������܂��B
�@�x���}�[�N�����́A�o�s�`�w���ψ���i��X�I�q�ψ����A�S�W�l�j�̎d���̂ЂƂŁA�e�N���X�ɂS�l����ψ��̂����Q�l���x���}�[�N�W�ł��B���N�A�T�N���̌W�����܂Ƃߖ��߂邱�ƂɂȂ��Ă��āA���N�x�͐X���������S�l�������̒��S�ł��B �@�S�V�N�̊Ԃɔ|��ꂽ�������@�������p���A��Ƃ͑��₩�ł��B�e�����Ń}�[�N���W�߂��x���}�[�N�W�̂��ꂳ���́A�����`���[���ֈړ����A�w�N���ƂɃe�[�u�����͂�Ń}�[�N���d�����܂��B�d�������}�[�N����Ђ��Ƃ̗e��ɓ���āA�X��������ɂ͉��U���܂��B�����P���Ԃقǂ̊����́A�d�������l�ɂ��x�Ⴊ�Ȃ��ƍD�]�ŁA���ꂳ���́A�u�}�[�N���W�߂ɋ����֍s���ƁA�N���X�̕��͋C��q�ǂ������̕��i�̂܂܂̗l�q��������܂��v�ƁA�����̃����b�g��b���Ă��܂��B 
�@�_���v�Z�́A�S�N���ȉ��̌W�����S���ĉƂōs���܂��B�O�̌��Ɏd�������}�[�N���p�̑܂ɓ���ėp�ӂ��Ă����A�A��ۂɂ����n���܂��B�Z�����搶�����ɔz�����āA���W�O���Ɂu�����͎��W���ł��v�Ə������J�[�h���A�x���}�[�N�W�̎q�����S�C�̐搶�ɓn���̂��H�v�ł��B�搶�����͎��W���ɔ����ċ����O�̃I�[�v���X�y�[�X�Ɋ���z�u����ȂǁA�������T�|�[�g���Ă��܂��B�X�コ��́u�n��̐l�������M�S�Ƀ}�[�N���W�߁A�w�Z�֓͂��Ă���܂��v�Ƙb���Ă��܂����B  �@����܂łɃx���}�[�N�a���ōw�������̂́A���N�`���[�A���v��}���`�ЂȒi�ȂǁB�ŋ߂��b�c���W�J�Z�ƃr�f�I�J�����A��֎ԁA�|�n���܂����B�u�g�D�Ƃ��Ē��N�����p����Ă��邱�Ƃ͑f���炵�����Ƃł��B�������A������������Ă���M�S���ɂ͓���������܂��v�ƁA���C���q���Z���͘b���Ă��܂��B �@�E���̂����ׂɂ���n���P�R�T���N�̊w�Z�B���Ɛ��̒��ɂ́A�l�n�`���p�ق�n�݂������c�g�⏗�D���V����q�����܂��B�n��ɂ́A�T���̎O�ЍՁA�W���̃T���o�J�[�j�o���A�P�P���̎���ՂȂǁA�`�����������Â��A���������͎O�ЍՂŎq���݂�����S���A����Ղʼn̕����������ȂǁA�n�敶�����w�тȂ���A�����̐S�ӋC�g�Ŋ�������Ă��܂��B �s�ʐ^�ォ��t �E�n�ƑO�A�����ő҂��Ă��邨�ꂳ���Ɏ����Ă����x���}�[�N�܂���n���������� �E�����`���[���ʼn�Ђ��Ƃ̗e��Ƀ}�[�N������w���ψ���x���}�[�N�W�̊F���� �E���S�ɂȂ��Ď��g��ł���T�N���̃x���}�[�N�W�A�X��������i���j�ƚ��䒼�q����B���䂳��ɂ��Ă���̂͊����̋L�^����������������s�䓌��̐��w�Z�� |
�� 400���_�B���Z��K�˂܂����I
�e�Ǝq���͂����킹�Ĕ��߂��w����錧�}�Ԏs�F�����w�Z
|
|
�@�S�O�O���_��B��������錧�}�Ԏs�F�����w�Z�i��ؗT�Z���A�V�T�O�l�j�̃x���}�[�N�����́A������Ƃo�s�`���͂����킹�Ď��g�݁A���̂W�N�ԂɂP�O�O���_��ςݏグ�܂����B

�@��������W�{�����e�B�A�ψ���͂T�A�U�N���̂Q�P�l�B���W�܂�����Ĕz��A�������ƂɃ|�X�^�[���đS�Z�����ɋ��͂��Ăъ|���܂��B�����̈ψ�����̎��ԂɁA�e��������}�[�N�ƃC���N�J�[�g���b�W��������A�ł���͈͂ʼn�ЕʂɎd�����܂��B���c�������͂o�s�`�Ɉ����p���܂��B �@�o�s�`�̒S���͌����ψ���B�e�N���X����P�`�Q�l�̌v�R�Q�l�̂��ꂳ���ł��B�����̈ψ�����̌�A�w�Z�ɏW�܂��č�Ƃ��܂��B���̂X�����Ɏn�߂ĂP���Ԃقǂō�Ƃ��I���A���Ƃ̐����͕��S���ĉƂōs���܂��B ![��ؗT�Z���A���v�×��]�����i�O��E����j�Ƌ��ɂS�O�O���_�B��������ēc�ψ����Ǝ��ʕ��ψ����i�����j](/img/report/schoolvisit1/0812/400tomobe02.jpg) �����̑傫�ȃ|�C���g�́A�e�����S�������Ђ����߂Ă��邱�ƁB�����̓s�x�A�����_���̃}�[�N���a�T���̑䎆�Ɏ��X�ɒ����āA�W�v�ɔ����邩��ł��B�P�N��ʂ��ē�����Ђ������̂ŁA��ƌ������ǂ��Ƃ����������b�g���B�w�Z�ł̍�ƂɎQ���ł��Ȃ����́A�}�[�N���q�ǂ��Ɏ����A���Ă��炢�A�����̎d���͂��Ȃ��܂��B�����͂X���ƂQ���̔N�Q��ł��B
�����̑傫�ȃ|�C���g�́A�e�����S�������Ђ����߂Ă��邱�ƁB�����̓s�x�A�����_���̃}�[�N���a�T���̑䎆�Ɏ��X�ɒ����āA�W�v�ɔ����邩��ł��B�P�N��ʂ��ē�����Ђ������̂ŁA��ƌ������ǂ��Ƃ����������b�g���B�w�Z�ł̍�ƂɎQ���ł��Ȃ����́A�}�[�N���q�ǂ��Ɏ����A���Ă��炢�A�����̎d���͂��Ȃ��܂��B�����͂X���ƂQ���̔N�Q��ł��B�@�E�����ł͐搶�������C���N�J�[�g���b�W���W�߁A���H���ł͒��������������₵�Ȃǂɂ��Ă���}�[�N���W�߂Ă���܂��B�Z��ɂ���R���r�j�������ʂɃ}�[�N���͂��܂����B�u�S�O�O���_�B���͑吨�̊F����̋��͂̂��A�v���ēc�疾�ψ����Ǝ��ʔ��b�q���ψ����͘b���Ă��܂��B���H�A�x���}�[�N�a���Ŕ��������H�p�̔��߂𒅂āA���H���Ԃ̂P�N����������ăN���X���[�g�̐H��ɐ���t�����Ă��܂����B  �@�w�Z�n���͂P�X�O�P�i�����R�S�j�N�B�R�N�O�Ɏs���������ŗF��������}�Ԏs�ɂȂ�܂������A�s���ꎙ�����������w�Z�ł��B�߂��̌��������a�@�ƘA�g���Ĉ�Ë���Ɏ��g��ł��܂��B���y����������ŁA��S�R��}�[�`���O�o���h�o�g���g���[�����O�֓����ŋ��܂���܁B�o�s�`�L����N�A��錧����L��E�m�h�d�R���N�[���ŗD�G�܂��܂����B �s�ʐ^�ォ��t �E�w�N���ƂɊ����͂݁A�}�[�N���d����������ψ���̂��ꂳ�� �E��ؗT�Z���A���v�×��]�����i�O��E����j�Ƌ��ɂS�O�O���_�B��������ēc�ψ����Ǝ��ʕ��ψ����i�����j �E�^�V�������߂𒅂Ĕz�V���鋋�H���Ԃ̂P�N�������������錧�}�Ԏs�F�����w�Z�� |
�� 400���_�B���Z��K�˂܂����I
�{�����e�B�A���ϋɓI�ɋ��������s��c��R�����w�Z
|
 �@�ɂ��₩�ȏ��X�X����X�[�p�[�Ȃǂ��������ԑ�X�w����������ƂT���A����w����ɓ���ƊՐÂȏZ��X�ŁA�������������������͋C�ɕ�܂�Ă��܂��B�����s��c�旧�R�����w�Z�i�A�������Z���A�U�R�O�l�j���S�O�O���_��B�����܂����B��c����ł͂U�Z�ڂ̒B���ł��B
�@�ɂ��₩�ȏ��X�X����X�[�p�[�Ȃǂ��������ԑ�X�w����������ƂT���A����w����ɓ���ƊՐÂȏZ��X�ŁA�������������������͋C�ɕ�܂�Ă��܂��B�����s��c�旧�R�����w�Z�i�A�������Z���A�U�R�O�l�j���S�O�O���_��B�����܂����B��c����ł͂U�Z�ڂ̒B���ł��B�@�x���}�[�N�^���ɎQ�����ĂS�V�N�A�o�s�`�����ψ���i�X�u�t�q�ψ����ƏH�R�����q�ψ����A�T�R�l�j�𒆐S�ɐi�߂Ă��܂��B�P��̍�Ƃɕ����ψ��ƃ{�����e�B�A�����킹�ĂR�O�l����S�O�l���Q�����ċ��͂��Ă��邱�Ƃ��A�x���}�[�N�^����グ�������ł��B�N�R��A�w�Z�Ő�����Ƃ���_���v�Z�����āA���̓��̓��ɔ������Ă��܂��B 
�@�������������ŁA�Q�O�O�T�N�ɂ́u�j�@�n���W�O���N�A���@�R�����w�Z�o�s�`�v�ƕ������ꂵ���A��P�O�O���~������u�{���₫�̂P�D�Q�ڒ����a���ہv�Ɛ�p����w�����Ă��܂��B �@�X�u�ψ����ƏH�R�ψ����́A���߂Ęa���ۂ����Ėڂ��P�����Ă��܂��B�u�^����Ŋ��Ă������h�ȑ��ۂ��A�x���}�[�N�ł̂��������Ƃ͒m��܂���ł����B�������������ŁA�ւ��n�Z��C�O�Ȃǂ֖𗧂Ă��A�Љ�v���ł��邱�Ƃ���݂ɂȂ�܂��v�Ƙb���܂��B 
�@�u���ꂳ���́A�q�ǂ��̋���֊S���[���A�w�Z�ւ̎v���������������A�����ɂ����͓I�ł��v�ƎO��ȕ��Z���͘b���Ă��܂��B �@�o�s�`�����ŁA�p��{�����e�B�A�̕����N�C�Y�`���Ŋy�����b���A�V�тȂ���w�ԉp�ꊈ����A�u�{�̉ԑ��v�̕��X���s���ǂݕ������Ȃǂ�����܂��B�u�{�̉ԑ��v�̃����o�[�́A�Ǐ����Ԃɂ����߂̖{���A������Â炵���|�X�^�[�ŁA�L���ɓW�����ďЉ�鑼�A���̉��x�ݎ��Ԃɂ��ǂݕ����������Ă��܂��B  �@�����ł́A���N�u�C�̓��v�Ɂu�A�N�A�t�F�X�^�v���s���Ă��܂��B�~�J�����̋C�����̗ǂ���̂��ƁA���h���̃v�[������̃|���v�����Ŏn�܂�A�����Ɏq�ǂ������̊����������オ��܂��B�ӂ��ʂ��������ɐ����Ԃ��ł����ς��ƂȂ�A�q�ǂ������͗����ŋ삯���A�e���搶���C���t���Ƃт������ɂȂ�Ȃ���A�y���ނ̂������ł��B�u�G�R���I�����q���I�R�����I�v�Ɩ��t���A�v�[���̐��̓���ւ��𗘗p���ăC�x���g�ɂ���̂́A�ƂĂ����j�[�N�ȃA�C�f�A�ł��B�o�s�`���n��Ƌ��Ɋw�Z���x���Ă���p�����������܂��B �s�ʐ^�ォ��t �E�E����A���Z���A�S�O�O���_�̊��ӏ�����X�u�ψ����A�H�R�ψ��� �E�吨�ōs���W�v��Ƃł́A�w�N���������̐l�ƒm�荇����̂Ŋ��邻���ł��i�R�����j �E�W�O���N���L�O���čw���̋{���ہA�ƂĂ����h�ł� �E�P�Q���̂����ߐ}���́A�N���X�}�X�̃f�B�X�v���[�ŏЉ�Ă��܂����������s��c�旧�R�����w�Z�� |
�� 400���_�B���Z��K�˂܂����I
�吨�̃T�|�[�^�[���}�[�N�����s�������c���w�Z
|
|
�@���s������̈�c���w�Z�i���ѐM���Z���A�X�S�X�l�j���S�O�O���_��B�����܂����B�Q�����ĂS�V�N�B�o�s�`�w�N�w���ψ���̃��[�h�ʼn���̑����������ɎQ�����A�x���}�[�N�^���͐����ł��B����̘e����������ƁA�x���}�[�N�����Őݒu�����傫�ȃ\�[���[�d�g���v������m�点�Ă��܂����B
![���эZ���Ƌ��ɂS�O�O���_�B������Ԃo�s�`�w�N�w���ψ���̊F����B������r�c���q����A���R�m�q����A���㎞�q����A�P�l�����Ċp�c�Ђ�݂���A�]����������](/img/report/schoolvisit1/0812/400ida01.jpg)
�@�o�s�`�w�N�w���ψ��̂����w�N���̂U�l�������̒��S�ł��B�U�A�P�O�A�Q���̔N�R��A�}�[�N���W�߂Đ����A�������Ă��܂��B�����̓����́A�}�[�N�����̎�͂��u�o�s�`�����T�|�[�^�[�v�̂��ꂳ���Ƃ������ƁB��葽���̉�����o�s�`�����ɎQ���ł��邽�߂̃V�X�e���ŁA�x���}�[�N�̃T�|�[�^�[�͊e�w�N�ɂR�O�l�قǂ��܂��B�Q�w�N�����N�P���Ƃɓ�����܂��B�Ăт����̃v�����g�s������A�e�����̉���{�b�N�X����}�[�N���������Ƃ̏���������ȂǁA�~���Ȋ�����}��̂��w�N�w���ψ������ł��B��Ƃ͌ߑO���̂Q���Ԕ��قǂł��B �@���W���ʂ̕����j�[�N�ŁA�N���X�ʂɃJ�[�g���b�W�������}�[�N�̃O�������Ŕ��\���܂��B�P�O���̍ő��͂T�N�T�g�̂P�R�O�O�����A�S�Z�łP�S�O�P�O��������܂����B�u�������Ĕ����炢�x���}�[�N����������W�܂�ƌ��\�ȏd���ɂȂ���̂ł��ˁv�Ƃ̃R�����g�ɂ��Ȃ����Ă��܂��܂��B�}�[�N�̎��W���ԁA�S�C�̐搶���������������ɐ��������A�N���X��ۂƂȂ��ă}�[�N�W�߂ɑł�����ŁA������グ�Ă��܂��B 
�@�x���}�[�N�a���ʼn��y���◝�Ȏ��ɐ�@���������A�T�b�J�[�S�[�����Q�N�����čw������ȂǁA�����̐��ʂ���X�ł��B�w�N�w���ψ����̊p�c�Ђ�݂���́u�T�b�J�[�S�[���͎��ƂŊ��p����A��J���Ď��g�b�オ����܂����v�Ƙb���Ă��܂��B �@�w�Z�n���͂P�X�T�U�N�B�Q�N�O�̂T�O���N�L�O�ŁA�n��Ǝ��������͂��ċʉ���ȂǂŎ���������A���������z�����d�ݔ����w�Z�̎����ŁA���N�p�l���𑝂₵�Ă��܂��B���̊����͌��́u��T�Ȃ���V�G�l���M�[�܁v����܂��܂����B �s�ʐ^�ォ��t �E���эZ���Ƌ��ɂS�O�O���_�B������Ԃo�s�`�w�N�w���ψ���̊F����B������r�c���q����A���R�m�q����A���㎞�q����A�P�l�����Ċp�c�Ђ�݂���A�]���������� �E�x���}�[�N�a���ōw�������T�b�J�[�S�[���Ɗp�c����i���j�ƒr�c�����s������̈�c���w�Z�� |
�� 400���_�B���Z��K�˂܂����I
�Q�i�K�̐����ɍH�v�A�W�v���e�Ղ����l�s����敶�ɏ��w�Z
|
|
�@���l�s�̕��ɏ��w�Z�i�r�c�K�Y�Z���A�U�V�V�l�j���A�S�T�N�̎��g�݂łS�O�O���_��B�����܂����B��N�ĂɂQ�P�w�������̂�����́A���Ƃ��w�����Ă����ċx�݂́u�؍H�����v�Ŋ��A�x���}�[�N�����̐��ʂ�傢�ɃA�s�[�����܂����B

�@���i���͂o�s�`�w�N�w���ψ���B�e�N���X�ɂP�l���̍��v�Q�O�l�̂��ꂳ���ł��B�����Q�W���Ƀ}�[�N�����W���A�Q�i�K�Ő������܂��B�܂������̃N���X�̃}�[�N�������A���ĉƂŎd�����A�����_�����P�O�����ɃZ���e�[�v�łȂ��܂��B��������琔���ĂQ��ڂ̖ؗj���ɁA�ƂŐ��������}�[�N����������đS�Z�������킹�A����ɂP�O�O�����ɂ��܂��B�������Ă����ƁA�V���ƂR���̔������ɁA�W�v���e�Ղɂł��邩��ł��B��Ƃ͌ߑO���̂Q���ԂقǂŏI���A���������}�[�N�́A�������L�^���ĉ�Еʂ̃P�[�X�Ɏ��߂ĕۊǂ��܂��B���������ɉ���܂�n���ă}�[�N���W�߂܂����A�����I�ɂȂ�Ȃ��悤�ɁA�܂ɂ͊w�N�Ƒg�ƃi���o�[�������L�����āA�����Ė��O���������݂܂���B���N�̎��g�݂ŁA�l�X�ȍH�v�����܂�Ă��܂��B 
�@�������͂Q�N�ɂP�x�̃y�[�X�ł��B�O�W�N�x�͂̂�����̂ق����M����Q�P�ƍ��ӂ��N���[�i�[�U����w�����܂����B�u�ׂ�����Ƃł����A�y����ł��܂��v�Ɩ命����ψ����B�u�����������q�ǂ��������g���Ċ��ł���p������ƁA�������Ă悩�����Ǝv���܂��v�Ɖ����䂤�q���ψ����͘b���Ă��܂��B�r�c�Z���́u�𗧂��̂��Ă��������A���肪�����B����Ŏq�ǂ������ɂ��S�O�O���_��B���������Ƃ�`�������v�Ƙb���Ă��܂����B 
�@�P�X�T�P�N�ɗׂ̋��w�Z���番�����ĊJ�Z�B�Z���̗R���ƂȂ����u���Ɂv�͂����߂��ł��B����n�斄�����Ƃ̈�Ő������ꂽ�u�C�̌����v�������ĂT���قǂ̂Ƃ���ɂ���A���N���������͏c����NJ����ŁA���̑��`�Â���Ɏ��g��ł��܂��B�n���̋��t����͂���ꂽ�}�_�C��J���n�M�A�V�}�C�T�L�A�E�c�{�ȂǁA�����p�̐��������\���̐����Ŏ���A�W�������u���ɐ����فv�́A�w�Z����������f���炵���ݔ��ł��B �s�ʐ^�ォ��t �E������ׂ肵�Ȃ���y������Ƃ���o�s�`�w�N�w���ψ���̂��ꂳ�� �E�x���}�[�N�a���Ŕ��������ӂ��N���[�i�[������命�ψ����i���j�Ɖ������ψ��� �E�����p�̐��������ώ@�ł���u���ɐ����فv�͋M�d�ȋ���ݔ��ł��B���̂͒r�c�Z��������������l�s�����̕��ɏ��w�Z�� |
�� 300���_�B���Z��K�˂܂����I
������Ƃo�s�`�����͂��Đ����������S�R�s��Ώ��w�Z
|
|
�@�������S�R�s����Ώ��w�Z�i�n糐��i�Z���A�U�P�Q�l�j���A�x���}�[�N�^���ɎQ�����ĂS�S�N�łR�O�O���_��B�����܂����B��Ώ��̓����́A������̃{�����e�B�A�ψ���i���Ĉψ����A�T�N���ƂU�N���̂Q�S�l�j�Ƃo�s�`���ψ���i�����ʑ��ψ����A�Q�Q�l�j���͂����킹�Ċ������Ă��邱�Ƃł��B
 �@�{�����e�B�A�ψ��������A�N���X�ŕ�����z�z���ĉ���B���P�T���̏W����̎��Ԃ��g���A�d������Ƃ����Ă��܂��B�x�ݎ��Ԃ��A����I�ɗ��č�Ƃ����Ă���q�ǂ������邻���ł��B���̌�A�o�s�`���ψ����O���i�P�A�R�A�T�N�j�ƌ���i�Q�A�S�A�U�N�j�ɕ�����e�S��A�W�v��Ƃ��s���܂��B�����͔N�Q��ŁA���ψ���̖������������쐬���A�搶�������z�����Ă��܂��B �@���K�˂������́A�q�ǂ����������̍�Ƃ������Ă���܂����B�e�[�u���̏�ɍL�����}�[�N�̒��ŁA�ڂɕt�����̂��u���[�̂P�O�O�_���T�����A���}�[�N�ł��B���Ɏq�̃}�[�N�Ő��\������悤�ł��B�������v���A�q�ǂ������ƈꏏ�ɓ_���𐔂��Ă݂�Ɓu�P�O�O�_���T���ʼn��_�v�̖₢�ɁA�����Ɏ�������u�T�O�O�_�v�Ɠ����B  �u�T�O�O�_�̘A���}�[�N���P�U���ł́v�B������ƊԂ�����u�W�O�O�O�_�v�Ɗ��������ȏΊ�ł��B�����͓_���̑����Ƀr�b�N���A���̃}�[�N�����ɏW�܂�܂��B���y���j�����́u���������Ă���R�N���̕ی�҂���̊��Ǝv���܂��v�Ɗ��ӂ��Ă��܂����B
�u�T�O�O�_�̘A���}�[�N���P�U���ł́v�B������ƊԂ�����u�W�O�O�O�_�v�Ɗ��������ȏΊ�ł��B�����͓_���̑����Ƀr�b�N���A���̃}�[�N�����ɏW�܂�܂��B���y���j�����́u���������Ă���R�N���̕ی�҂���̊��Ǝv���܂��v�Ɗ��ӂ��Ă��܂����B�@�S���ɂ͎��W�A����̔N�Ԍv�悩��A���i�w���̂��m�点�Ƃ���Ȃǂ́u���ւ�v��N�W�s���鑼�A�L�ł��N�S��A���͂��Ăт����Ă��܂��B�܂����Ɛ��̕ی�҂��p�����ē͂��Ă���邻���ł��B�Q�O�O�S�N����P�P��̃e���r���w�����A������e���r��\��ɗ��ł��܂��B  �@�{�����e�B�A�ψ���ł́A�x���}�[�N���W�̑��ɋʂ̎���������S�A�T�N�O����s�Ȃ��Ă��܂����B�S�Z������ی�҂ɋ��͂��Ăт����A�W�܂����ʂ������Ɋ����A�����Ԓ~���Ă��܂����B�Q�O�O�W�N�U���A�u���������̏Z�ޒ��ɉ������Ԃ����������v�ƁA�q�ǂ��������ӌ����o�����������ʁA�����̓��ʗ{��V�l�z�[���u�������v�ɁA�u�Ԃ����U��v��܂����B�q�ǂ������̓w�͂��������сA���{�݂ő��掮���s��ꂽ�l�q���n���V���Ɍf�ڂ���܂����B�u���������ʂ̋ʂ��P�J���ɏW�߁A�Ԃ����Ƃ���ς������v�Ƃ����{�����e�B�A�ψ��̊��z���ڂ��Ă��܂��B �s�ʐ^�ォ��t �E�{�����e�B�A�ψ��Ƃo�s�`�̊��ψ����͂����킹�R�O�O���_�ɂȂ�܂��� �E�q�ǂ������͓_���̑������Ɏq�̃}�[�N�����đ��тł��B �E���N�̓w�͂��u�Ԃ����U��v�ƂȂ�A�z�[���̊F����ɂ����Œ����܂����i��Ώ��w�Z�j���������S�R�s�̑�Ώ��w�Z�� |
�� 300���_�B���Z��K�˂܂����I
�v�����ƍ�{�������ǂ��R�O�O���_�B����錧�����s�v�����w�Z
|
|
�@��錧�����s�̋v�����w�Z�i��ԓ֎q�Z���A�S�Q�T�l�j���A�R�O�O���_��˔j���܂����B�x���}�[�N�^���ɎQ�����ĂS�P�N�A�����s���ł͂X�Z�ڂł��B

�@�v�����z�[���y�[�W�ɂ́u�����m�������鏬�w�Z�B�P�Q�����Ƃ����̂ɖ{�Z�̐���ɍ����������炢�Ă��܂��v�Ƃ���A���K�˂����P�Q���T���A���N�t�Ɠ~�̂Q��Ԃ��炩���y���܂��Ă���Ă���l�G�����A�[���̋�̉��A���ȋC�Ȕ������ł����B �@�w�Z�͊C����R�O�b�̍���Ɉʒu���Ă���A�⓹���炳��ɂP�O�U�i�̊K�i��o��A���ǂ蒅�����Z��ɂ́A�R�{�̃V���{���c���[�u���₫�̖v�����т��Ă��܂��B 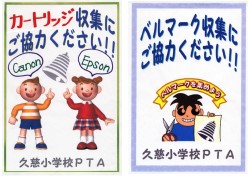 �z�b�g�ꑧ���A���U��Ԃ�Ƌv�����`����]���邱�Ƃ��ł��A���̌i�F�͐S��a�܂��Ă���܂��B�u�Z�납��̒��߂͈��S�I�ɂ��I��Ă��܂��v�Ɛΐ쌫�i�����͘b���Ă��܂����B
�z�b�g�ꑧ���A���U��Ԃ�Ƌv�����`����]���邱�Ƃ��ł��A���̌i�F�͐S��a�܂��Ă���܂��B�u�Z�납��̒��߂͈��S�I�ɂ��I��Ă��܂��v�Ɛΐ쌫�i�����͘b���Ă��܂����B�@���������܂Ƃ߂�̂́A��T�w�N�ψ���i��ؗ�q�ψ����j�̂S�l�ł��B�d�����A�W�v��Ƃ́A�N�W��s���A�w�N���Ƃɓ��������߂Ċe�w�N�ψ��i�Q�V�l�j����Ƃ��܂��B��T�w�N�ψ���́A�����̊w�N���̐����̂ق��P�O���ƂQ���̔N�Q��A�S�̂����v���Ĕ������܂��B 
�@��T�w�N�̈ψ��̊����́A�܂����c�ōs���Ă��������ɏo�Ȃ��邱�Ƃ���n�܂�܂��B�Q�����Ă̊��z��^���̈Ӌ`�Ȃǂ͊w�Z�L�Ɍf�ڂ��鑼�A�N�R�s�̃x���}�[�N�ւ�ŁA�x���}�[�N�̐������W�̂��肢�A���������̓��e�Ȃǂ荞���͂��Ăт����܂��B �@�n��̌𗬃Z���^�[��R���r�j�ȂǂU�J���ɁA�|�X�^�[�ƈꏏ�ɉ������ݒu�A�����̃}�[�N���W�܂�܂��B�g�i�[�ƃC���N�̃J�[�g���b�W�́A�v�����w�Z�Ɠ������ƍ��Z��������������A���W�_�����L�т�傫�ȃ|�C���g�ł��B 
�@�܂��A�߂��̊�ƁA�������\�����[�W�����Y����x���}�[�N�ƃC���N�J�[�g���b�W�����Ă��������B�������܂�܂����B���Ђ́A�s���̍�{���w�Z�ւ����Ă���A�����w�Z�ł��R�O�O���_���ɒB�����Ă��܂��B���̂Q�Z�͂Ƃ��ɖh�ƃu�U�[���w�����Ă���ȂNj��ʓ_�������A��ԍZ���́u���݂����ǂ��Ȋw�Z���m�ł��ˁv�Ƙb���Ă��܂����B �@�����ł́A�n��Ő���Ȑ��Y�Ƃ̊������A�����I�Ȋw�K�̎��Ԃɐ��Y�����Ƃ����e�[�}�ŁA���`���s���Ă������̎d�����A�����l�ɕ����ăZ����������A���m���Ƃ����l�B�̖������S�̘b������A�u�����v�̈�{�ނ��͌^�̋����g���A�^���̌��������肵�Ă��܂��B���̂ق��A�ی�҂Ǝq�ǂ��������u�������{�����e�@�v�Ƃ��āA�C�ݐ��|�����Ȃ��璪�������V�т����āA�y����������߂������Ƃ������ł��B �s�ʐ^�ォ��t �E���ӏ������؈ψ����Ƒ�T�w�N�ψ��̊F����B�E���͊�ԍZ�� �E�Ăт����|�X�^�[�̂������Ń}�[�N�̏W�܂肪�Ⴂ�܂� �E�����͎��ƌ��J�̓��A���l�̕����J�[�g���b�W�������ė��ĉ������܂����B�F���͓I�ł� �E���Y�����ŁA���Ǝ҂⒇���l�ɕ����ē���̎d����̌��i�v�����j��������������s���v�����w�Z�� |
�� 300���_�B���Z��K�˂܂����I
�V�Z�ɂɂR�O�O���_�̊��ӏ���錧�����s��{���w�Z
|
|
�@��錧�����s�̍�{���w�Z�i���R����Z���A�W�P�X�l�j���A�R�O�O���_��˔j���܂����B�����s���ł͂P�O�Z�ځB�s���̋v�����w�Z�Ɠ����̒B���ł��B
 �@�Q�O�O�W�N�R���A�V�Z�ɂ������A���z���C�����Z�ɂ��܂ߊe�����Ɉړ����₷���Ȃ�A���ӂ�g�����̈�ق⑽�ړI�X�y�[�X�A�ً}��m�点��h�o�z�[���A�o���A�t���[�g�C���ƍŐV�ݔ��̍Z�ɂɕς��܂����B�P�P���Q�P���A���z���C�L�O�u���ӂ̏W���v���s��������̂Ƃ���ɒB���̒m�点�ł��B�u�^�V�����̂ʂ����肪����Z�ɂɊ��ӏ�������āA�݂Ȃ���ɂ��m�点���邱�Ƃ��ł��A��������Ƃł��v�ƁA���R�Z���A����T�搶�͘b���Ă��܂����B �@�x���}�[�N�^���ɎQ�����ĂR�W�N�A�����𗦂���̂͂o�s�`�x���}�[�N�����ψ���i�A���a�q�ψ����A�P�O�l�j�ŁA�X���ƂP���̔N�Q��A������\��ɐ�����Ƃ��s���܂��B�d������Ƃ́A�x���}�[�N�����ψ������X������A����������Ă���ɂR�����炢�܂ł����čs���Ă��܂��B�_���ʂɎd������̂́A����Ɏ����A�萮�������܂��B�܂Ƃ߂��}�[�N�����c�ɑ��鏀���͈ψ����̒S���ł��B  �@����̓����⊈�����ʂ̂��m�点�́A�s����ł����x���}�[�N�ψ�����ŁA�N�Q�s���Ă��܂��B �@�n��ɂ́A�w����̂Q�̗X�ǂɉ������u���A�F���狦�͂��Ă��������Ă��܂��B���ɁA�߂��̊�ƁA�������\�����[�W�����Y����x���}�[�N�ƃC���N�J�[�g���b�W�̊�����A�B���̑傫�ȗ͂ƂȂ�܂����B�u�ی�҂�n��̋��͂̑f���炵����m��܂����v�ƐA���ψ����͘b���Ă��܂��B �@�܂��A�����̎����͒n��Ɏx�����āA�o�Z���牺�Z�܂ł�������Ă��������Ă��܂��B���Ƃł͔N�ԂP�O�l�قǂ̋߂��ɂ�����L���X�g����w����w�����A�Q�X�g�e�B�`���[�Ƃ��Ď��Ƃ��T�|�[�g���Ă��������Ȃǂ��āA�w�K�̌��ʂ����߂Ă��邻���ł��B 
�@��{���̍Z��ɂ́A����ˌÕ��Q�̂P�����̈�̂������c�����Ύ����c���Ă��܂��B���̓x�A�n��Ɗw�Z�̃V���{���Ƃ��āA�V�����Õ��ۑ��ɂ�����đ�ɊǗ�����܂����B���ӂɂ́A�O����~���P��E�~���R���Ȃ�Õ��Q������܂����B���̕ӂ���x�z���Ă��������̕悾�����ł��B���������w�Z�̕~�n�����H���Ȃǂŏ��ł��Ă��܂����݂́A���̂P�����̐Ύ��݂̂ɂȂ�܂����B�����甭�����ꂽ�品�E�S���̕����n��A���g��A�����i�́A�����s���y�����قɕۊǂ���W������Ă��܂��B �s�ʐ^�ォ��t �E�O��E����A����搶�A���ӏ�����A���ψ����A���R�Z���A�x���}�[�N�S�����c�q�搶�B���͂o�s�`�x���}�[�N�����ψ���݂̂Ȃ��� �E�̍��肪���Ė��邢�����͉��K�ł����A�d������Ƃ̎��͐^�����̂��̂������ł� �E�n��E�w�Z�̃V���{���B�M�d�ȐΎ��ƌÕ��ۑ��ɂł���������������s����{���w�Z�� |
�� 300���_�B���Z��K�˂܂����I
�}�[�N�́u�������D�ނ��َq�Ɖe���v��ʌ������s���㏬�w�Z
|
|
�@��ʌ������s�̐��㏬�w�Z�i����N�j�Z���A�U�R�O�l�j���R�O�O���_��B�����܂����B�����s���ł͏��߂Ă̒B���Z�ł��B

�@�x���}�[�N�^����i�߂�̂́A�o�s�`�������i��ލ_�������A�Q�O�l�j�ł��B�w�Z�ł̃x���}�[�N�����͔N�X��A�����������Q�O���[�v�ɕ��������ɍs���܂��B�_���v�Z�͎���̍�ƂƂ��Ă��܂��B�S�������Е��S�����߂�̂̓W�����P���ł��B�}�[�N�̗ʂ�������ЂƏ��Ȃ���Ђ�ڕ��ʂŐl�����ɕ����A�������l����D���ȎR������Ă����܂��B�}�[�N�̔����͂X���ƂQ����\��ɁA�����A���������ŏI�`�F�b�N�����đ���܂��B�Q�O�O�W�N�x�A�_���v�Z�ɑ䎆���g���A�}�[�N���Z���e�[�v�Œ�����@�ɕς��܂����B�u�_���v�Z�ƃ}�[�N�̊ԈႢ����ڂł킩��A�\�����ǂ��̂ł��Ў��̕��Ɉ����p�������v�Ƒ�ޕ����͘b���Ă��܂��B �@�������ł̓x���}�[�N���W����̍ۂɁA�`���R���[�g��|�e�g�`�b�v�X�Ȃǂ̂��َq�ނ̃}�[�N�������W�邱�Ƃ��C�ɂȂ�A�����������u�ǂ�Ȃ��َq�v���u�ǂ̂��炢�H�ׂĂ��邩�v���e�[�}�ɒ������܂����B  �ی�҂ɃA���P�[�g���Ƃ蕪�͂��u�x���}�[�N�̎��W����݂������́v�Ƒ肵�āA�Q�O�O�V�N�x�̊w�Z�ی��ψ���Ŕ��\�����܂����B�u�����q�Ƃ��َq�̊W�v�̒������e�́A���َq�Ɋ܂܂�铜���Ɖ����A�����Ȃǂɂ��āA���l�ɕK�v�ȂP���̐ێ�ʂ���Ƃ肷���ɂ��̂ւ̉e���܂ł��A�z�[���y�[�W�ȂǂŒ��ׂ����܂����B���ʁA�����肤��u�����K���a�v��u�G�l���M�[�ʂƏ���̊W�v�A��Ƃ��āu�w���V�[�ȃ��V�s�Ɨ��������v�܂ōs���������ł��B����Z���́u�ǂ��܂Ƃ߂Ă��苻���̂��鎑���ł��B����ψ������^����܂����v�Ƃ��ꂳ����̓w�͂��]���Ă��܂����B�������̓x���}�[�N���������łȂ��A���N�����������ɂ����g��ł��܂��B
�ی�҂ɃA���P�[�g���Ƃ蕪�͂��u�x���}�[�N�̎��W����݂������́v�Ƒ肵�āA�Q�O�O�V�N�x�̊w�Z�ی��ψ���Ŕ��\�����܂����B�u�����q�Ƃ��َq�̊W�v�̒������e�́A���َq�Ɋ܂܂�铜���Ɖ����A�����Ȃǂɂ��āA���l�ɕK�v�ȂP���̐ێ�ʂ���Ƃ肷���ɂ��̂ւ̉e���܂ł��A�z�[���y�[�W�ȂǂŒ��ׂ����܂����B���ʁA�����肤��u�����K���a�v��u�G�l���M�[�ʂƏ���̊W�v�A��Ƃ��āu�w���V�[�ȃ��V�s�Ɨ��������v�܂ōs���������ł��B����Z���́u�ǂ��܂Ƃ߂Ă��苻���̂��鎑���ł��B����ψ������^����܂����v�Ƃ��ꂳ����̓w�͂��]���Ă��܂����B�������̓x���}�[�N���������łȂ��A���N�����������ɂ����g��ł��܂��B�@���㏬�͂V�R�N�O�Ɍ��Ă�ꂽ�ؑ��Z�ɂł��B�V�䂪�����A�L����K�i�̖̂ʂ����肩��A���j�Ɠ`�������������܂��B 
�@�����ɂ́A���k�n���Ŋ����r�k�u�b�T�W�R�U�R�v�̃v���[�g�ƁA�f�B�[�[���@�֎ԁu�c�d�P�O�P�P�v�����邱�Ƃ������ł��B�r�k�́A����w���߂����Ƃ���P�T�N�ԁA�Z��̕Ћ��ɒu����A�̂�т�Ɨ]���𑗂��Ă��܂����B�P�X�W�V�N�́u�������ܔ�����v�̍ہA�����S���łr�k�^�]���ĊJ���邱�ƂɂȂ�A�u�r�k�p���I�G�N�X�v���X�v�Ƃ��ĕ������܂����B���̖��c�̃v���[�g�́A��ɍZ�����ɏ����Ă��܂��B�u�Z��ɂ������r�k������w�ɉ^��鎞�́A�ƂĂ��₵���C�����Ō�����܂����v�Ƙb������N�]�o�s�`��́A�e�q�Q��Ńx���}�[�N�����Ɋւ��A�R�O�O���_�B���̊�т��Q�{�ł��B �s�ʐ^�ォ��t �E�u�Q�O�O�W�N�x����������S�����ėǂ�������v�ƂR�O�O���_�̒B������ԊF����B�����͏���Z���A��ޕ����i���ׁj�A����o�s�`��i�E�ׁj �E�������肪�ǂ��a���ō�Ƃ��܂��B�u���c�Q�T���N�L�O�ő���ꂽ�����p���m�[�g�v���Ɏg���A�ߋ��̗��j��m�邱�Ƃ��ł��A���N�A�V���������̐S�����Ղ̊��ł� �E��Е��S�����߂�W�����P�����A�a�C���������Ƃ݂Ȃ���y�������ł�����ʌ������s�����㏬�w�Z�� |
�� 300���_�B���Z��K�˂܂����I
�x���}�[�N�Ǝ������݂Ŏ����Â����_�ސ쌧���͌������͌����w�Z
|
|
�@�R�O�O���_��B�������_�ސ쌧���͌����̓��͌����w�Z�i�����n�Z���A�U�O�W�l�j��K�˂�ƁA�}�[�N�����邨�ꂳ���ׂ̗ło�s�`��������c���ł����B�x���}�[�N�̂ق��V������ʂȂǂ̎������݂�������Ď��������A
 �q�ǂ������̂��߂ɗV��Ȃǂ������Ă������ψ���̊����́A�o�s�`����ۂƂȂ��Č㉟�����Ă��܂��B
�ꐳ�o�s�`��́u�����Ɏ��g��ł��������v�Ƙb���Ă��܂����B
�q�ǂ������̂��߂ɗV��Ȃǂ������Ă������ψ���̊����́A�o�s�`����ۂƂȂ��Č㉟�����Ă��܂��B
�ꐳ�o�s�`��́u�����Ɏ��g��ł��������v�Ƙb���Ă��܂����B
�@����ψ���́A�k�v�یO�ψ��������P�W�l�ł��B������͖�����Q���j���B���X��������A��Â���̕��ޗp�̔���H�i�������Ă����g���[�Ȃǂ��g���ă}�[�N���d�����܂��B�}�[�N��ۊǂ��闧�h�Ȑ����ɂ��������Ă��āA�����悭��Ƃ��ł��܂��B�d�������}�[�N�͕��S���āA�Ƃœ_���v�Z���A�����܂łɊw�Z�ɖ߂��ƁA�k�v�ۈψ����������ɋL�����Ĕ������܂��B  �����͖����ł����A��w�N�ƍ��w�N�����݂ɒS�����A���S��������Ȃ��z�����B���W���ʂ����v�����g�ɂ́A�x���}�[�N�Ǝ������݂����ʂŁA����ɒi�{�[����A���~�ʂȂǎ�ޕʂɎ��v�����ڂ��āA���S�������Ă��炤�H�v�����Ă��܂��B�o�s�`�̃��`�x�[�V���������߂邽�߂ɁA�O�W�N�x�͐搶��������A���P�[�g���Ƃ��čw���ڕW��ݒ肵�܂����B���ꂪ���ʂ��グ�āA��N�P�Q���ɂ͖ڕW�Ƃ����v�[���t���A�𒍕�����܂łɂ������܂����B�搶�������A�T�̎��Ԋ��Ɏ��W������������Ċe�ƒ�֘A�����Ă����ȂǁA�������T�|�[�g���Ă��܂��B
�����͖����ł����A��w�N�ƍ��w�N�����݂ɒS�����A���S��������Ȃ��z�����B���W���ʂ����v�����g�ɂ́A�x���}�[�N�Ǝ������݂����ʂŁA����ɒi�{�[����A���~�ʂȂǎ�ޕʂɎ��v�����ڂ��āA���S�������Ă��炤�H�v�����Ă��܂��B�o�s�`�̃��`�x�[�V���������߂邽�߂ɁA�O�W�N�x�͐搶��������A���P�[�g���Ƃ��čw���ڕW��ݒ肵�܂����B���ꂪ���ʂ��グ�āA��N�P�Q���ɂ͖ڕW�Ƃ����v�[���t���A�𒍕�����܂łɂ������܂����B�搶�������A�T�̎��Ԋ��Ɏ��W������������Ċe�ƒ�֘A�����Ă����ȂǁA�������T�|�[�g���Ă��܂��B
 �@�u�o�s�`�����͊y�������邱�Ƃ���v�ƌ�����̍l�������f����āA�x���}�[�N�����͂��������݁A������ׂ肵�Ȃ���̊y�������͋C�Ői�߂��܂��B�o�s�`����̏����q������A�R�N�ԉ���ψ����߂ē��e���悭�m���Ă���̂ŁA�������₷�����ł��B�k�v�ۂ���́u�F�ƏW���̂͊y�����A�ψ����������A�Ŋw�Z�̗l�q��������܂����v�Ƙb���Ă��܂����B �@���̒��S�ɂ���n���P�R�U�N�̊w�Z�ł��B�P�N���͈��̕����A�S�N���͒��E�݂ȂǁA�L���Ȏ��R�������p�������犈���Ɏ��g��ł��܂��B �s�ʐ^�ォ��t �E�}�[�N���������ψ���̊F����B�ׂło�s�`�����̉���s���Ă��܂��� �E���������}�[�N��ۊǂ��鐮���ɂƖk�v�ۈψ��� �E�x���}�[�N�ōw�������v�����^�[����ɂ���o�s�`�����������_�ސ쌧���͌������͌����w�Z�� |
�� 300���_�B���Z��K�˂܂����I
�u�F�̂��߂Ɂv����������ő傫�Ȑ������쌧���{�s���쏬�w�Z
|
|
�@���������̗͂Ńx���}�[�N�^����i�߂Ă���A���쌧���{�s�̐��쏬�w�Z�i�a�c�N�Y�Z���A�U�R�U�l�j���R�O�O���_��B�����܂����B�u���̎q���������[�_�[�̎��ɑ���B���ł��āA�{���ɂ悩�����v�ƌږ�̐_�c�搶�͖ڂ��ׂ߂Ă��܂��B
 �O�W�N�x����̃��[�_�[�́A�x���}�[�N�ψ����̏㞊����ƕ��ψ����̏��R�N�i�O���͂��̋t�j�A�����ď��L�̐���N�ł��B�S�`�U�N���Q�O�l�̃x���}�[�N�ψ������������āA�ϋɓI�Ɏ��g��ł��܂��B
�O�W�N�x����̃��[�_�[�́A�x���}�[�N�ψ����̏㞊����ƕ��ψ����̏��R�N�i�O���͂��̋t�j�A�����ď��L�̐���N�ł��B�S�`�U�N���Q�O�l�̃x���}�[�N�ψ������������āA�ϋɓI�Ɏ��g��ł��܂��B�@�O�W�N�x�̓}�[�N����������W�߂邽�߂ɁA�������Ɂu�x���̓��v��ݒ肵�܂����B�e�����ɐ�p�̔���u���|�X�^�[�ŌĂт����A�����̃N���X�Ǝo���w���ɏW�܂����}�[�N���A�ӔC�������ĉ�����܂��B���҂ǂ�����ʂ������āA�O���ɏW�߂��}�[�N�͖�U�O�O�O���B�P�Q���ɂ͂P�P�T�O�����W�܂��āA���������͎艞���������Ă��܂��B  �@��������}�[�N�́A�����ɂ����鎙����ɂ܂Ƃ߂Ă����A�x�ݎ��Ԃ́u���Ԋ����v�ňψ������Ŕԍ��ʂɎd�����܂��B���Ƃ̐����͖����̎�������ōs���܂����A�����̎d�����Ɠ��ł��B���[�_�[����Ƃ̐i����݂āA�d���������邩�����𐔂��邩�����߁A�ψ������Ƀ}�[�N��z���B����ɏ]���āA�ψ������͈ꐶ�����ɐ������܂��B�Ƃ̐l���L���ō���Ă��ꂽ��������̔����A������Ƃɑ劈��ł��B�_���ʂɖ����𐔂������́A�e�������ʂ����ɏ����o���A��������v���ďW�߂������Ɠ_�����o���܂��B�N�x���ɂ́A�P�N�ԂɏW�߂��������Z�������Ŕ��\���邱�Ƃɂ��Ă��܂��B �@���H�A������������A���P�[�g���Ƃ��Ď蓮�����M������P�U��w�����A�����Ă��Ȃ��N���X�ɔz��܂����B���̑��̃N���X�ɂ͎��ɔ����������邱�Ƃɂ��Ă���A�����ɂׂ͍₩�Ȕz��������܂����B�u�ψ��͊F�̂��Ƃ��l���Ċ������Ă��܂��v�Ɛ���N�B�u�o����܂ő�ς���������ǁA�F�ƈꏏ�Ɋ�������̂͊y�����v�Ə㞊����B  �u���������M������A�F�����ł���Ă悩�����v�Ə��R�N�B�x���}�[�N�^���̃{�����e�B�A���_����������~�߂āA���g��ł��܂����B
�u���������M������A�F�����ł���Ă悩�����v�Ə��R�N�B�x���}�[�N�^���̃{�����e�B�A���_����������~�߂āA���g��ł��܂����B�@�S�O�N�O�ɁA���ꏬ�w�Z�Ɛ_�я��w�Z���������ĊJ�Z�B���ꏬ�w�Z�̃x���}�[�N�����������p���܂����B�S�N�������S�ɂȂ��čs���Ă���A���~�ʂ�L���b�v�Ȃǂ̃��T�C�N���^���A�i�q�b�i���{�ԏ\���j�ψ���̘V�l�z�[���Ƃ̌𗬂ȂǁA�{�����e�B�A����������Ȋw�Z�ł��B �s�ʐ^�ォ��t �E�ψ�����̎��ԂɃ}�[�N������x���}�[�N�ψ��̎������� �E������ɔ�����ꂽ�x���}�[�N�����ɂ��͂ރx���}�[�N�ψ���̃��[�_�[�����Ɛ_�c�搶�i�E����Q�l�ځj �E�͂����킹�čw���������M����������ĊF�ŋL�O�B�e ������������쌧���{�s�̐��쏬�w�Z�� |
�� 300���_�B���Z��K�˂܂����I
�}�����X�Z�Ŏ����ƕی�҂��A�g���m����{�s��{���w�Z
|
|
�@��������������̈��m����{�s����{���w�Z�i�i�����Z���A�P�R�R�V�l�j�̃x���}�[�N���[�_�����A�P�X�W�P�i���a�T�U�j�N�̉^���Q���ȗ��̗v�łR�O�O���_��˔j���܂����B�Q�O�O���_�ɓ��B����܂ł͂Q�O�N������܂������A���̌�̂P�O�O���_���V�N�ԂŐςݏグ�܂����B

�@�ߔN�̊����Ȋ����́A������̃x���}�[�N�ψ���i�T�A�U�N���̂Q�V�l�j�Ƃo�s�`�������i��C���������A�Q�O�l�j�̘A�g�̐��ʂł��B�x���}�[�N�ψ����������ȒP�Ȏd�����܂ł��s���A�����������d�����A�W�v�������Ă��܂��B �@�S�Z�����́A�����Ƃ��Ė����Q���܂łɊe�N���X�ɂ��������Ƀx���}�[�N�����܂��B�x���}�[�N�ψ���������W�߁A�����������ԍ��̃x���}�[�N��ʂɎ�蕪���܂��B���������͂P�A�T�N���̕ی�҂ŁA�e�N���X�Q�l�ł��B���P��w�Z�ɏW�܂��Ďd�����A�_���A�W�v�����܂����A���ꂼ����ԍ������܂��Ă���̂ŁA�������ɓs���������ꍇ�͎���ō�Ƃ��܂��B  �@�x���}�[�N�̉�����͍Z����̎����Z���^�[��s�����Ȃǂɂ��u���A�L����ʂ̋��͂����ł��܂��B�����̔N�ԑ��[���́A�ŋ߂R�N�A���Ō����x�X�g�Q�O�ȓ��ɂ���A�O�V�N�x�̓\�t�g�h�b�W�{�[����ړ������_�ŁA�v�[���p�x���`���w�����܂����B �@�����������������ł́A�搶�Ǝq�ǂ��̂Ȃ���A�q�ǂ����m�̂Ȃ��肪�����Ȃ�Ȃ��悤�w�߂Ă��܂��B���̈���u�̐��̂���w���E�w�N�E�w�Z�Â���v�ŁA����Ȃǂ̋@����Ƃ炦�Ă͑S�̍��������A���͂��������Ƃ̑�����w��ł��܂��B �@�܂����É��s�̃x�b�h�^�E���Ƃ��Ď��������}�����Ă���̂��A�Z�ɂ̑ϐk���Ƒ��z�H�����i��ł��܂��B�O�W�N�R���ɂ́A�^���p�@�ȂǏ���G�炳���ɍ�Ƃł������ݔ��𐮂����u�h���C�����v�̋��H�����������܂����B���݂͑��ړI����������R�K���Ă̐}���������ݒ��ł��B �s�ʐ^�ォ��t �E�N�x���ɐ��ʂ��グ�悤�ƁA������ƂɏW�����镟�������̂��ꂳ��� �E�x���}�[�N��S�����镟�����͂P�A�T�N���̕ی�҂ō\�����Ă��܂�������������m����{�s�̑�{���w�Z�� |
�� 300���_�B���Z��K�˂܂����I
�Q�N���ȏ�͉�Дԍ��ʂɃ}�[�N�������{��s�������쏬�w�Z
|
|
�@���{��s�������쏬�w�Z�i�����Ύ��Z���A�U�Q�V�l�j�̃x���}�[�N���W�_�����A�^���ɎQ�������P�X�W�O�N����̗v�łR�O�O���_���܂����B
�@�x���}�[�N��S�����Ă���̂��o�s�`�x���}�[�N�ψ���i����R���ψ�����P�X�l�j�ŁA�e�N���X�P�l�̊w���ψ��ō\������Ă��܂��B 
�@�����͂P�w���ɂP��̃x���}�[�N�T�ԂɎ������A�Q�N���ȏ�͋��^��Дԍ��ʂɓ���Ă��܂��B�q�ǂ��̈ӎ������߂邽�߂ɍs���Ă��邻���ł��B�Z����̃X�[�p�[�A�h���b�N�X�g�A������قɂ��������u���Ă܂��B �@�o�s�`�͗��T�Ɏd�������������܂��B�P�N���̕��̎d�����A�Q�N���ȏ�̂��`�F�b�N���܂��B�ԍ��ʂɎd���������邾���ŁA��͎���Ɏ����A��Q�T�Ԃقǂ��ďW�v�p���ɗ��ʃe�[�v�ɓ\���Ďd�グ�A�ŏI�W�v���Ĕ������܂��B �@�����͂Q�O�O�X�N�ɑn���R�O���N���}���܂��B�}���V�������݂ȂǂŎ������N�X�����Ă��܂��B�Z�ɑ��z���i��ł���A�o�s�`�ł̓x���}�[�N�a���ŐV�����p�̊|�����v�����낦�邱�Ƃɂ��Ă��܂��B�W�҂͑n���R�O���N���j�����̂悤�ȃx���}�[�N�R�O�O���_�B�������ł��܂��B �s�ʐ^�t �E�x���}�[�N�̎d������Ƃ𑊒k���Ȃ���s���o�s�`�x���}�[�N�ψ���̂��ꂳ�������{��s�̋����쏬�� |
�� 300���_�B���Z��K�˂܂����I
�e�ƒ�ʼn�ЕʂɎd����������Ɍ����̎s����w�Z
|
|
�@���Ɍ����̎s�̏���w�Z�i�c����T�Z���A�X�P�U�l�j�̃x���}�[�N���W�_�����R�O�O���_���܂����B�x���}�[�N�^���ɎQ�������P�X�W�U�N�ȗ��̗v�ł����A�Q�Q�N�Ԃł̂R�O�O���_�B���̓n�C�y�[�X�B�������A�e�ƒ납���ЕʂɎd�����ďo���Ă��炤�A�Ƃ������Ƀ��j�[�N�Ȃ��̂ł��B
 �@�o�s�`���ƕ��i���c�䂩�蕔����P�X�l�j���S���B�W�v�͔N�V�炢�B�W�v���̂P�T�ԂقǑO����A�e�����ʼn���܂�����܂��B �@����܂͓����ȃr�j�[���̏��܂ŁA�P���P���ɋ��^��Ђ̔ԍ����ӂ��Ă���܂��B�S�Е����Z�b�g�ɂȂ��Ă���A���ꂪ�e�N���X�Q�Z�b�g����܂��B��������ԂɎ����ɉA���ꂼ�ꂪ����Ŏd�������āA��Еʂ̏��܂ɓ���ԋp���A���ɉd�g�݁B �@�x���}�[�N���o���i�K�Ŏd�����ς݁A������V�X�e�������Ă���̂͋ɂ߂Ē��������Ƃł��B�]���̈ꊇ������Ăo�s�`���d������ɂ́A���������������ߑ�ρA�Ƃ������Ƃ���A���̕����ɂȂ����悤�ł��B���ꂾ�ƁA�ǂ��������i�Ƀ}�[�N�����Ă��邩�e�ƒ�ŕ������Ă��炦�₷���Ƃ������_������܂��B �@�W�߂�ꂽ�}�[�N�͎��ƕ������P�O���P�O��ɏW�v�p���ɓ\��t���A�i�C�������̃}�[�N�̓z�b�`�L�X�ŗ��߂܂��B�Ō�̓_���v�Z�͐������������Ċw�����ɔ������܂��B �@�x���}�[�N�ʐM�͂Q�O�O�W�N�x����A���ߍׂ��������ڂ���悤�ɂ��Ă��邻���ł��B �s�ʐ^�t �E�x���}�[�N�d�����p�̉���܂���ɂ���o�s�`���ƕ��̎��c�䂩�蕔���ƁA�d������Ƃ����镔���݂̂Ȃ����Ɍ����̎s�̏���w�Z�� |
�� 300���_�B���Z��K�˂܂����I
���ւ̂������ׂɉ���{�b�N�X�ޗnj���a�S�R�s�Ћˏ��w�Z
|
|
�@�ޗnj���a�S�R�s�̕Ћˏ��w�Z�i�R�c�b�q�Z���A�T�T�S�l�j�ŁA�P�X�U�R�N�̃x���}�[�N�^���Q���ȗ��̎��W�_���̗v���R�O�O���_���܂����B�R�O�O���_�B���͌����P�X�Z�ڂł��B
 �@�x���}�[�N�S���̂o�s�`�����������i�哇�_�]�����A�P�P�l�j�͊w�N����Q�l���I��܂��B���W�͔N�S��i�U�A�X�A�P�Q�A�Q���j�ő�P���j���Ɏ�������Ă��炢�܂��B���ւ̂������ׂɉ�����������Ă���̂ŁA���W���ȊO�ɂ�������܂��B���W���Ƃ���ȊO�͔��X�̊����������ł��B �@�������ߑO�X�����`�P�Q���܂łɉ�ЕʁA�_���ʂɎd�����܂��B���̂��ƕ������W�v���Ĕ������܂��B����܂łɁA�������Ȃǂ��w�����Ă��܂��B �@�Ћˏ��͂P�O�N�ȏ�O���炠�����^���𑱂��Ă���A�e�N���X�̎��������Ő���Ȃǂɗ����A�o�Z�̎����ɂ����������Ă��܂��B�܂��o�s�`�͂��ߒn��̋��͂��M�S�ł��B �s�ʐ^��t �E�x���}�[�N�̎d���������邨�ꂳ�����ޗnj���a�S�R�s�̕Ћˏ��w�Z�� |
�� 300���_�B���Z��K�˂܂����I
���[�h���u�x���}�}�v�ɂn�a���Q���L�������{�����̕{���������w�Z
|
|
�@�L�������{�����̕{���������w�Z�i�n糂����ݍZ���A�X�O�S�l�j�̂P�X�V�P�N�̃x���}�[�N�^���Q���ȗ��̎��W�_���̗v���R�O�O���_���܂����B�{�����e�B�A�O���[�v�u�x���}�}�v�����S�ɂȂ��Ă��܂��B
 �@�u�x���}�}�v�͐X���a��������\�ɂP�U�l�B�q�ǂ������w�Z�𑲋Ƃ������ꂳ�U�l���c���Ă��邱�Ƃ��u�x���}�}�v�̓�����\���Ă��܂��B���R����{�����e�B�A������ł��B�ȑO�͂o�s�`�w�������ψ���S�����Ă��܂������A�P�N���ł̓X���[�Y�ɂ����Ȃ��ƁA�L�u���W�܂�U�N�قǑO���獡�̃{�����e�B�A�Ԑ��ɂȂ�܂����B �@�u�x���}�}�v���x���Ă���̂��Q�O�O�l�̃T�|�[�^�[�ł��B�����̎d���������ɁA�Q�w�N���T�|�[�^�[�̋��͂܂��B �@�q�ǂ��������T�A�U�N���̃��T�C�N���ψ����d�������̑�x�e�̎��ԂɎ�`���܂��B�C���N�J�[�g���b�W�ނ̎d���������S�ł��B �@����܂łɃz���C�g�{�[�h��{�[���Ȃǂ��w�����܂����B�u���낢��Ȃ��̂��������Ă��炢���肪�Ƃ��v�ȂǂƊ��ӂ̕ւ肪�x���}�}�ɂ��͂��Ă��܂��B �@�{���������͂Q�O�O�W�N�P�P���ɑn���S�O���N���}��������B�Z��ł̂������^����W�J����Ȃnj��t���ɁA�������Ƃ��d�_�ɂ�������Ɏ��g��ł��܂��B �s�ʐ^�t �{�����e�B�A�O���[�v�u�x���}�}�v�̂��ꂳ���B��ɂ́u��Ǝ菇�v�Ȃǂ����L�����{�����̕{���������w�Z�� |
�� 300���_�B���Z��K�˂܂����I
�d�����͊w�Z�A�W�v�͎�����k��B�s���������w�Z
|
|
�@�k��B�s���������w�Z�i�F��O�Z���A�T�W�P�l�j�����������S�U�Z�ڂ̗v�_���R�O�O���_��B�����܂����B�Q���S�V�N�ڂł��B
�@�o�s�`�̒S���͊w�N�ψ���i���c�����q�ψ����j�ŁA�����o�[�͊e�N���X����P�l�̌v�P�X�l�B�����Q�T������A�����Ɏ��W�܂�z��A�N���X���ƂɒS�C�̐搶��������Ă���܂��B�W�܂����}�[�N�́A�����̑�Q���j���Ɉψ����w�Z�̃����`���[���Ő����E�d�������܂��B�d���������}�[�N�͈ψ�������ŏW�v���A�N�Q��A�S�̏W�v���Ĕ�������d�g�݂ł��B  �@�����`���[���̍�Ƃ́A����ߑO�P�O������Q���Ԓ��x�B�P���̍�Ɠ��Ɏ�ނł��ז�����ƁA�����ȉ~�`�̃e�[�u�����͂�ŁA�\���l�̂��ꂳ������ЕʁA�ԍ��ʂɃ}�[�N�̎d�����̍Œ��ł����B�u���������ւ�ł��ˁv�Ɛ���������ƁA�u�فX�Ƃ��킯�ł͂Ȃ��̂Łc�c�v�ƁA�ψ����̏��c���������ʂ�A�݂�Ȃ�����ׂ肵�Ȃ���́A�Ȃ��₩�ȕ��͋C�B�������₦���A��ƂƂ�������̃T�[�N�������̂悤�ŁA�x���}�[�N�^���̃��b�g�[�̂ЂƂu�����Ȃ��v������v���ł����B �@�������w�Z�́A�s�����⏬�q��ɋ߂��s���S�����q�k��̏Z��X�ɂ���܂��B�R�N�O�Ɋw�Z�̌��đւ����n�߁A�O�W�N�S���ɂ͐V�Z�ɂ������A���݂̓O���E���h�����H�����i��ł��܂��B�Z�Ɋ������L�O���āA�O�W�N�ĂɃx���}�[�N�a���ŁA�e�w�N�P��ȂǍ��킹�ĂV��̋Ɩ��p�N���[�i�[���w�����܂����B�O�W�N�x���ɃO���E���h����������̂ŁA�s�����Ă���e���g���w������\��ł��B �@�������w�Z�̃��j�[�N�Ȋ����̂ЂƂɁA�Z��̎蒆�w�Z�Ƃ̍������|������܂��B���N�A�U�N���ƒ��w�Q�N�����ꏏ�ɗ��Z�̊Ԃ�ʂ錴���Γ��̑|�������Ă��܂��B�O�W�N�͂X���Q�Q���ɍs���A��S�O�O�b�̗Γ��̑��ނ����������A���ݏE���������肵�܂����B�n��ɖ𗧂{�����e�B�A������̌����邾���łȂ��A�����w�������������A�b�������M�d�ȋ@��ɂ��Ȃ��Ă��邻���ł��B �s�ʐ^�t �����P��̎d������ƁB�����`���[���ɏW�܂����ψ��́A������ׂ肵�Ȃ����͋x�݂܂��� ���k��B�s�̐������w�Z�� |
�� 300���_�B���Z��K�˂܂����I
����ŒS���������d�����ƏW�v����s���m�c���w�Z
|
|
�@����s���m�c���w�Z�i�������Îq�Z���A�Q�X�X�l�j�������Q�S�Z�ڂ̗v�_���R�O�O���_��B�����܂����B�Q���S�R�N�ڂł��B
�@�o�s�`�̒S���͕������i�{�����������A�X�l�j�ł��B���w���ɂP��A�}�[�N���W���Ăт�����u���m�点�v�����g�v��S�����ɔz��A�w�Z�ɏW�܂����}�[�N�́A�������w�N���ƂɎ���Ŏd�����E�W�v���܂��B�V�A�P�Q�A�Q���̍�Ɠ��Ɋw�Z�̂o�s�`���ɏW�܂�A�S�̏W�v���A�������闬��ł��B����ł��炩���̍�Ƃ�����ł���̂ŁA�S�̏W�v�͂Q���ԑO��ŏI���邱�Ƃ��ł��邻���ł��B�W�v���ʂ́A�N���X���Ƃ̎��W���ʂƂƂ��ɍڂ����v�����g��z���ĕ��܂��B  �@�������̒S���̓x���}�[�N�̂ق��A�ی�Ҍ����̍u����ȂǕ������Ƃ̊J�Âł��B�O�W�N�͋ߗׂ̂Q�����w�Z�Ȃǂƈꏏ�Ɂu�H��v���e�[�}�ɂ����u������J���܂����B �@�m�c���w�Z�́A�ۊO�̃X�|�[�c�N���u����������ł��B�O�W�N�͌��~�j�o�X�P�b�g�I�茠���ŁA�j�q���D���A���q�͂R�ʂ̍D���т��c���A�j�q�͂O�X�N�R���ɂ���S�����Ɍ���\�Ƃ��ďo�ꂵ�܂��B �@�w�Z�́A�i�q����w����Q�L���]��̍���̏Z��X�ɂ���A�s������̔ɉ؊X�E�v�ċ����瑱������̓r���ł��B�X�����⓹�Ɍ��Ă��Ă��邽�߁A���ւ͂Q�K�ɂ���܂��B�Z�ɉ��̈ꕔ�����ԏ�ɂȂ��Ă��āA�ׂɂo�s�`��������A���H���璼�ڏo����ł���̂ł����A�n�����̂悤�Ɍ����܂����B �s�ʐ^�t �E�S�̏W�v�͔N�R��B���̓��͂U�l�̕������̂��ꂳ�Q���A�Ȃ��₩�ȍ�ƕ��i�ł��� ������s�̐m�c���w�Z�� |
�� 300���_�B���Z��K�˂܂����I
�����E�W�v�͖����P��Ŗ�Q�������茧�|���s�����|�����w�Z
|
|
�@���茧�|���s�����|�����w�Z�i�R���q���Z���A�T�R�Q�l�j���Q���R�O�N�Ō����Q�T�Z�ڂ̗v�_���R�O�O���_��B�����܂����B���茧�ł͂O�W�N�P�O������P�Q���ɂR�O�O���_�B���Z���S�Z�Ƒ������ł��܂��B
�@��F��i�o�s�`�j�̒S���͋��狳�{���i�y�i�ޗ��}�����j�ŁA�e�N���X�P�l�̌v�P�V�l�������o�[�ł��B�����P��A�S�����Ƀ}�[�N���W�܂�z��A����A�����E�W�v�����̓s�x�s���A�����͊w�����Ƃ̔N�R��ł��B  �@�����P��̐����E�W�v�́A�Z�ɂR�K�ɂ����F��ō�Ƃ��܂��B�d���������Ă�����A�Ƒ��̐��b�ɒǂ�ꂽ��̂��ꂳ��������̂ł����A����قڑS�������W�܂邻���ł��B��Ƃ͒��P�O������Q���ԑO��ƌ��߂Ă��āA���̓��ɏI���Ȃ��Ƃ��́A�S���ŋϓ��ɕ����A����Ɏ����A���č�Ƃ��܂��B �@�Z����̃X�[�p�[��a�@�Ȃǂɂ��������u�����Ă��炢�A�N�R��A�ł��m�点�����A�n��̐l�����ɋ��͂��Ăт����Ă��܂��B�����̍�Ƃƒn��̋��͂������āA���|�����ł́A�N�Ԏ��W�_�����������N�P�O���_�O��ŁA�|���s���ł͂Q�ʁA�����ł��x�X�g�P�O�̏�A�Z�ł��B�R�O�N�łR�O�O���_�B���Ƃ��������y�[�X�𗠕t���Ă���悤�ł��B �@���狳�{���́A�x���}�[�N�����̂ق��A�{�ݖK��̃{�����e�B�A��A�ӂꂠ���R���T�[�g�Ȃǂ�S�����Ă��܂��B�R���T�[�g�̂����Q�N�ɂP��J���A�ׂɂ��鐼�|�����w�Z�u���X�o���h���̉��t�͍D�]�ŁA�����E���k�̌𗬂ɂ��𗧂��Ă��邻���ł��B �s�ʐ^�t �E�����P��̐����E�W�v�B���狳�{���̂قڑS�����W�܂�A�M�S�ɍ�Ƃ��܂� �����茧�|���s�̐��|�����w�Z�� |