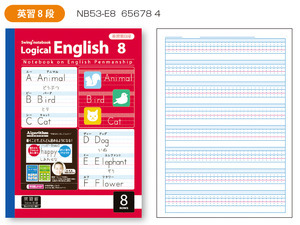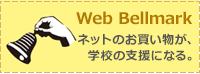ベルマーク運動説明会 5月22日(水)高松
(2019/06/17)印刷する
| 高松市立多肥小学校 安井睦人さん |

|

高松市立多肥小学校PTA会長の安井です。もしかしたら、私よりも皆さんの方が実務については知ってらっしゃる方が多いかとも思いますがよろしくお願いします。
まず初めにこちら、「たひまろ」ですが、これは多肥小学校のマスコットキャラクターです。
多肥小のめざす子ども像は、自分を磨く子、人と関わる子、未来をひらく子の実現に向け、心がけてほしいことを願い「た」高めよう学び、「ひ」広めよう仲間作り、「まろ」守ろうルールということで、このメッセージを込めたキャラクターです。本日はこのタヒマロと共に説明していきます。
県下第2位のマンモス校
まず少し多肥について説明します。
多肥校区は高松市中央やや南に位置する南北に約2.8キロ、東西1.4キロの非常に広い校区です。この校区の中には桜井高校、高松南警察署、南消防署などの公共施設があります。また、あまり知られてはいませんが多肥観音という日本でも珍しい木造の観音様があります。
元々は田園地帯で、10数年前に区画整理をした中で宅地化が進み、人口も増加している地区です。それに伴って小学校も右肩上がりで生徒数が増加しています。
今年1183人の小学生が在校しています。10年前は782人でした。さらに20年前は445人で、この20年で約3倍の増加となっています。県下でも第2位のマンモス校です。
子どもたちは生徒会を中心に自分たちで「優しさと活気あふれる多肥小」ということで毎朝だれでも参加できるボランティア活動をしています。タヒマロプロジェクトの一環ですが、朝の挨拶運動、朝玄関のところで行うお早うソング隊、さらに校内の清掃など、学校の授業とは別に児童会が自主的に行っています。

PTAと子どもクラブ
そんな子どもたちに負けじと私たち大人も活動しています。
保護者には二つの団体に属してもらっています。一つがPTA、もう一つが子どもクラブです。PTAは各校にあると思いますが、子どもクラブは前身が子ども会です。多肥校区は子ども会がどんどん衰退していって、地域との連携や安全対策などがなかなかうまくいかない、といったところで、学校の中に「子どもクラブ」ということで整備して、いま30班で地域との連携、安全対策を実施しています。
一方、PTAはPTAとしての原点に立ち返り、先生たちが学校の運営の中で困っていることのサポートを中心に、各専門部に分かれて活動しています。
ベルマーク活動は、教育環境部が担当しています。教育環境部は全部で36人。1学年6クラスあるので計36クラスから1人、専門部員を出してもらっています。この中から部長、副部長を中心にベルマークやPTA主催のバザーなどをやっています。
マークは毎月、カートリッジ等は常時回収
ベルマークの収集は、毎月月初めに一回集めています。それとは別に、インクカートリッジやテトラパックは常時回収ができるよう、玄関に子どもたちが持って来たらすぐに入れられる状態を作っています。
インクカートリッジやテトラパックは点数が高い上、家に置いておくと、ついついかさばって捨ててしまいがちなので、常時回収することにしました。テトラパックの場合、夏場に洗いが十分でないと臭い等の問題が発生して困ることがあるので、こうした点は丁寧に文書などで各保護者に協力をお願いするのがいいかと思います。
毎月のベルマーク収集では、マークを入れて持ってきてもらう各個人の封筒に、生徒が描いたイラストを学年ごとに統一して使っています。こうすることで、子どもと一緒に保護者もベルマークにより関心を持ってくれるようになりました。
また、専用の封筒を一年間使い続けるようにしています。封筒の大きさを決めてしまえば、中に入れるベルマークもそれに合わせて各家庭で切ってもらえる。負担を各家庭に分担できるように考えたためです。
仕分けは家に持ち帰って
仕分けは、学校に集まったマークを各専門部員に持ち帰ってもらいます。自宅でベルマーク活動ができるわけです。
家庭での作業は会社別、点数別に仕分けすることです。こうして分けたマークは台紙に貼っています。この段階で各家庭で一旦集計します。それをみんなが集まる部会に持ち寄って最終的に集計し、発送します。
こうすることで、小さいお子さんを抱えているお母さんや、働いているお母さんも、活動に参加できます。家でちょっと空いた時間に取り組んでもらえるように、家での作業が中心となるようにシフトしています。
一方で、この数年は人口こそ増加しながらも、ベルマークは約12万点を行ったり来たり、という状況です。
人口が増えても世帯数が増えないということもさることながら、作業をしてくれる皆さんに限界があるということが大きな原因だと思います。どれだけ集めたとしても、それを仕分けして集計し送るということになると、共働き世帯では辛い所もあるようで、どうしてもこの12万点が多肥小の実力ということになっています。
もちろん公共施設に置いてもらうという方法もありますが、これをやっても人員を割かないとそこに取りに行けないし、それを誰が集計するのかという問題もあります。広めるのはいいけれど、集めた後どうするのかが今の多肥小の問題点です。
作業量の面でも、台紙に貼るのを辞め、ジップロックに入れてそこに集計表を貼るという形でもいいのかもしれないけれど、家での作業を中心にすると、ミスをなくすように全体でチェックをしないといけない。どの方法を取るにせよ一長一短が出てしまいなかなか作業としては難しい現状です。
生活とのバランスを考えて
PTAの活動は時代と共に変化してきています。その中でも「できる人が、できる時に、できる事を」がいまのPTAを現している言葉であり、多肥小PTAもこの言葉を根本に置いて活動しています。
しかし、共働き世帯や子育ての人が中心となる関わり方は変化してきますし、ボランティアと生活のバランスを考える時に来ているんだと思います。
今後はウェブベルマークなども広く活用しながら、もっと楽にベルマークの運動をできるように頑張っていきたいと思っています。
本日はご清聴ありがとうございました。
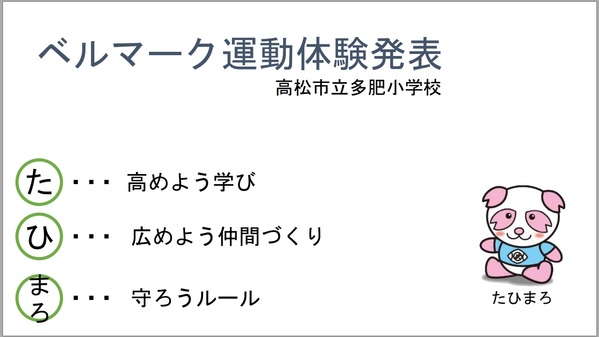
*画像をクリックすると、PDFでご覧になれます。
(パワーポイントを使って説明)
=サンポートホール高松 4階第1小ホール