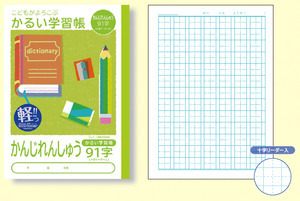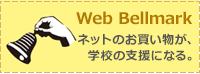ベルマーク運動説明会 6月12日(火)米子
(2018/06/29)印刷する
| 米子市立加茂小学校 左から 堀江美香さん(2017~2018年度副会長)、 大田裕美さん(2017年度書記)、 木下久美子さん(2017年度学年部長、2018年度監査)、 宮本清香さん(2017年度監査、2018年度学年部長) |

|
米子市立加茂小学校の「保護者と先生の会」の大田裕美と申します。
ベルマークと出会ったのは、私が小学生の頃でした。今と同じように小学校で集めていました。そして、息子、娘が保育園に通うようになり、再びベルマーク活動に出会いました。
さらに、加茂小学校へ入学し、またまたベルマーク活動と出会いました。これも何かのご縁。ベルマークと私は本日のこのような貴重な時間までつなげてくれました。どうぞよろしくお願い致します。
まず初めに、学校紹介です。
加茂小学校は、弓ケ浜公園、陸上自衛隊米子駐屯地、博愛病院と、充実した環境の中に位置しております。明治6年3月、当時の両三柳村と米原村をもって両三柳小学校を設置。明治20年4月に三柳尋常小学校、さらに昭和20年4月に加茂国民学校となり、その2年後に米子市立加茂小学校と改称され、現在に至ります。
児童数は5月末現在で520名となっています。
今日はちょうど、春のマラソン大会の日です。弓ヶ浜公園を子ども達は全員完走を目標に一生懸命走ります。
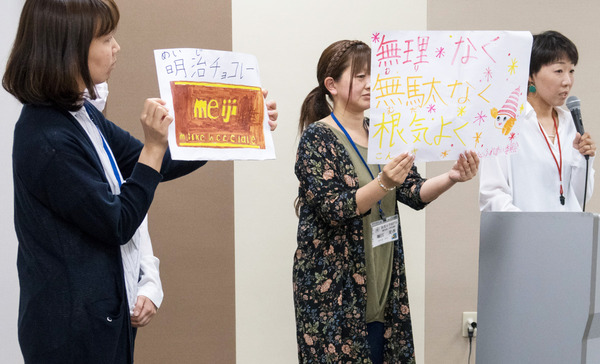
そんな子どもたちですが、1日7~8時間は学校で友達や先生方と共に生活しています。ここにあります学校教育目標「自ら学び 心豊かにたくましく 共に生きる子供の育成」をもとに。始業式では校長先生より「『快活な学校』をみんなで目指しましょう!」とお話ししていただきました。
快活とは「活気があり、主体的に行動する」「自分の居場所がある」「多くの出会いと学びがある学校」と教わりました。そして、5~6年生の児童で運営する委員会では、かもっこ計画委員会のメンバーが委員長を中心に、「快活」な学校にするための児童会スローガンを募集し、話し合って決定しました。「輝こう いつもニコニコ加茂っ子で 作ろう楽しい毎日を」です。
そのほか、学校支援ボランティア活動といって、生活や学習の支援、環境整備、登下校時の見守りなど、地域に作られた学校応援団の方々に見守って頂いております。
かもっこ計画委員会のほかにもたくさんの委員会があります。次にご紹介するのは『心ふれあい委員会』です。5~6年生の17人で、ベルマークの収集・仕分け、ベルマーク袋の作成と配布・回収、ベルマークに関するお知らせ、ポスター作りなどに取り組んでいます。
実は、昨年は息子が所属し、今年は娘がこの委員会に縁あって所属しております。先日、心ふれあい委員会の皆さんの活動の様子を拝見し、委員長にインタビューをさせていただきました。「この委員会を選んだ理由は?」と尋ねると、「募金活動や人のために役立ちたかったからです。ベルマークを完璧にそろえるように頑張ります!」と、とっても頼もしい答えが返ってきました。
心ふれあい委員会では、お知らせ係が低・中・高学年用にそれぞれ読みやすいように工夫をこらし、ベルマーク集めについてのお知らせ原稿を作成しています。ポスター係は、校内に掲示して呼びかけるためのポスターを作成していました。ベルマークの種類係は、ベルマークのついているものを絵にして、分かりやすいようにPRしました。
また、心ふれあい委員会のみんなで、昨年ベルマーク預金で購入した「キンボール」を、実演交えて全校児童の前で紹介しました。
過去には、デジカメ、マイク、大玉、ポンプ、スカットボーイなど、先生に相談して、学校に必要なものを購入してきました。
現在の加茂小のベルマーク預金は14万2794円です。

次に、保護者である私たちの紹介です。
「保護者と先生の会」とはPTAのことです。事業部、広報部、学年部、人権教育推進部の4つに分かれ、執行部員総勢18名。会長を中心に各部に副会長、部長をそれぞれ1名ずつおき、部員はそれぞれ2名程度です。その中で、学年部がベルマークも担当しています。
ベルマークだよりの発行は年3回。集め方、注意点、協賛企業の新規加入・脱退のお知らせ、ベルマーク預金残高の報告、購入品紹介、ベルマークに関する情報などを発信しています。
ちょっとした自慢話になりますが、2017年度の鳥取県集票ランキングで加茂小が見事1位に輝きました。スミフルの「バナージュをもらおう」に応募し、これまた見事当選! 学校のお弁当日にデザートとして全員に配りました。スミフルのホームページにも掲載されました。2016年にはベルマーク財団から累計集票400万点突破を表彰していただきました。「無理なく・無駄なく・根気よく」を合言葉に取り組んだ結果がこうして形になることは、大変励みになります。
続いて、ベルマークの集め方の紹介です。まず学校では、子どもたちが毎月、「こころふれあい委員会」の児童らが準備したベルマーク収集袋を持って家に帰ります。そして家庭で集めたベルマークを入れて、学校へ届けています。
保護者は学年部執行部の方を中心に、地元のスーパーや郵便局、公民館などにベルマーク収集ボックスを置かせてもらい、地域のみなさんのご理解、ご協力に感謝しながら、マークを回収しています。
次に、マークの「仕分け」です。心ふれあい委員会では全校から集めたベルマークの中で、とくに多い「日清」「キューピー」を中心に、委員会の限られた活動時間に仕分け作業をしてくれています。
一方、保護者は年2回の仕分け日を設け、意見交換や交流の場として2時間程度、学校の教室で仕分け作業をしています。子どもと一緒に参加する人も多く、親子のコミュニケーションの場にもなっています。
実は、泣ける秘話もあるんです。学年部の執行部の方々は自主的に、年2回の仕分け作業日とは関係なく、ベルマークの仕分けにコツコツと取り組んでいます。「無理なく」ではないかもしれませんが、常に「子どもたちのために」と、ベルマーク活動を生活の一部にするくらい熱心な方達を私は誇りに思います。
ネットでの買い物を通じて、ウェブベルマークも活用しています。
加茂小学校では毎年、「ベルカッチャ」といって、自宅でベルマークの集計作業にあたるメンバーも募集しています。毎年50人ほどの応募があります。「ベルカッチャメンバー」と書かれた袋には、「集計の仕方」「会社ごとに仕分けされたベルマーク」「独自のベルマーク集計カード」などが入っています。
メンバーには、「ベルカッチャアンケート」と題し、感想、問題点などを書いてもらい、改善に役立てています。これまで、こんな意見が寄せられました。
【良かった点】
・学校での作業は夜なのでなかなかに行けないが、ベルカッチャの作業なら自宅でできる。このような形で協力できてよかった。
・子供と一緒に作業できた。
・空いた時間に作業ができた。
・手書きのメモなどがすごくうれしかった。
【わかりにくかった点・改善点】
・説明に写真などを使ってほしい。
・小さいベルマークの集計が大変だった。

次にベルマークだよりの紹介です。これは、ここ数年で発行したベルマークだよりです。ベルカッチャのアンケート結果も掲載しています。
そして、「整理」です。集め、仕分け、会社ごとに集計されたら、ベルマーク整理袋へ詰めます。この時、「学校名」「住所」「PTA番号」「合計点数」「合計枚数」を記入していきます。ここが執行部の底力の見せ所です。総合計は電卓の達人が計算します。
袋詰め、計算が終わったら、学校の先生へバトンタッチ! ベルマークを財団へ送っていただきます。カートリッジも同じように学校へ集荷していただきますので、ベルマーク担当の先生へ依頼し、お世話になっております。
今後の課題について、心ふれあい委員会は「ベルマークを完璧にそろえたい」としています。私たち保護者は、仕分け作業への参加者や、地域協力の回収箱設置場所をさらに増やして、ベルマーク活動をもっとたくさんの方に知っていただき、地域全体で取り組めるようにできたらいいなと思っています。
顔を合わせれば、「ベルマークのことなんだけど」なんて自然に会話できる日が来ることを心待ちにしている今日この頃です。
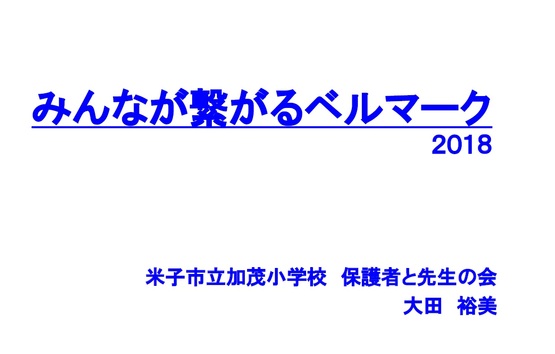
*画像をクリックすると、PDFでご覧になれます。
(パワーポイントを使って説明)
=国際ファミリープラザ 3階会議室B