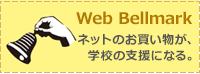ベルマーク運動説明会 5月30日(水)松本
(2018/06/08)印刷する
| 松本市立梓川小学校 左から、塚田春奈さん、米盛健さん、手塚絵理さん、 青木万里子さん |

|
おはようございます。本日、ベルマーク活動について説明させていただきます、松本市立梓川小学校の米盛と手塚です。よろしくお願いいたします。

最初に本校の紹介をさせていただきます。
梓川小学校は松本市中心部より西へ約8キロの地点に位置し、梓川がつくる扇状地の北側を学校区としております。
校区はたいへん広く、田んぼ、商業施設、リンゴ畑などで構成されております。リンゴ作りは地域を代表する産業です。また、松本市のベッドタウンとしてたくさんの住宅地が点在しています。

学校は昭和48年に梓小学校と倭小学校が統合して創立され、46年目を迎えます。長く南安曇郡梓川村の小学校として運営されてきましたが、平成の大合併により梓川村が松本市となり、松本市立梓川小学校となりました。近年宅地造成が進んだこともあり、学校規模は児童数900名を超え、県下でも有数のマンモス校です。
本校では開校以来「大地に立つ教育」を推進してきています。恵まれた自然、歴史や文化、人々との関わりの中で「生きる力」を育み、郷土を愛したくましく自立した人間になってほしいと願って学校運営がされてきました。
その願いをもとに、
「梓川の大地に根ざして 豊かに自立する子どもの育成
~あずさっ子 かしこく なかよく たくましく~」
という教育目標が掲げられ、子どもたちや先生方もそれに向かって日々学校生活を送っています。
近年では、特にマラソンや外遊びを通して体力向上を図る意識が高まり、朝や休み時間は多くの児童が外に出て積極的に体を動かしています。また、健康教育の一環として歯みがきに力を入れて取り組んでおり、昨年は「よい歯の学校」として歯科医師会から全国表彰を受けました。
続いてベルマーク活動についてお話しします。

本校でベルマークの収集が始まったのは20年前です。その間、集めた点数は、毎年県の上位に位置し、特に5年ほど前には県1位の実績を収めたと聞いております。学校規模にもよるのでしょうが、これまで児童のみなさんやご家庭で、こつこつと協力してくださったことがわかります。そのおかげで昨年度は累計200万点を達成することができました。
さて、本校でのベルマーク活動の中心は児童会のベルマーク委員会です。5・6年児童30名あまりからなり、ベルマーク収集のために主体的に活動しています。
各委員は自分のクラスと下級生のクラスに置くベルマークボックスを工夫して作り、週に一回、朝や昼休みに各教室で呼びかけを行って、たくさん集まるようにがんばっています。
集まったベルマークは、休み時間を利用して仕分けてくれています。廊下に、種類ごとの引き出しのついたケースが置かれてあり、委員の子どもたちが交代で作業に当たっているそうです。また、どのクラスで何点集まったか分かるように、集計結果はファイルにまとめているそうです。

昨年度は、ベルマークに対する全校の意識を高めるためにベルマーク週間も設定されました。その中で、朝の時間に全校集会が開かれ、委員によりベルマーク活動の意味や仕組みがクイズなどを交えて説明されました。
購入品についても全校の意見を聞きながら委員が中心に選んでいます。27年度は長縄跳び用の縄をクラス分、28年度は黒板消しクリーナーと体育館用のボール、昨年度は各クラスに配れるようにサッカーボール30個を購入しました。
点数の使い道ということで言えば、過去には東日本大震災の被災校に10万点寄付したこともあったそうです。これも委員会で話し合った結果だそうです。
こうした児童の主体的で前向きな姿を先生方も応援してくれています。例えば、家庭向けの「ベル通信」をつくって下さり、児童の活動の様子や購入品の状況などを家庭に知らせてくださることもあります。
次にPTAとしての関わりです。

本校PTAには「ほほえみ委員会」という部門があります。各クラスから1名の委員で構成されており30名ほどの組織です。ちなみに昨年までは「母親委員会」という名称でしたが、父親でも活動できるように「ほほえみ委員会」という名前に変更しました。
この「ほほえみ委員会」で、年に一度集計作業を行っています。 午前中2時間程度の作業です。
10年近く前のことですが、児童だけでは集計が追い付かず、未整理のベルマークが年々たまっていく状況があり、PTA作業と母親委員会の作業で全てを整理したそうです。以来、母親委員会の活動として位置づきました。
児童は当番制を設け、交代で整理に当たっていますが、作業が追いつかない分が出てきます。その分を「ほほえみ委員会」が全て整理集計し、児童の活動が滞らないように支えているわけです。
作業は、児童が種類ごとに分けた引き出しを取り出して、中身を整理し、集計します。引き出しを児童と共有していることで、児童の作業とのつながりが大変スムーズですし、児童の姿を思い浮かべながら、応援する気持ちで作業に取り組むことができます。

本校PTAとしては、ベルマーク活動が単に備品などの教育環境の向上につながるだけでなく、児童の主体性や社会性の育成にも生きる活動であると考え、そうした児童の活動を支えるという立場で、今後も児童とともにベルマーク活動に関わっていきたいと考えています。
以上で発表を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。
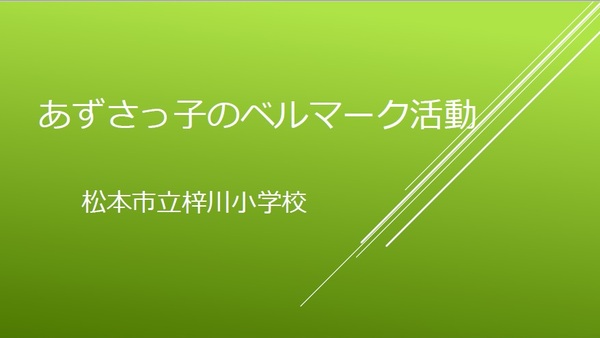
*画像をクリックすると、PDFでご覧になれます。
(パワーポイントを使って説明)
=松本市駅前会館 4階大会議室