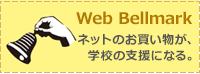クモっていいやつなんだ/京都・宕陰小中学校で理科実験教室
(2024/10/09)印刷する
京都市中心部から電車やバスを乗り継いで約1時間半。市の北西の愛宕山のふもとに、今回の「理科実験教室」が開かれた市立宕陰(とういん)小中学校があります。学校のそばには、美しい棚田や古い民家も残っていて、この地区は「京都の信州」ともいわれるそうです。
同校(明田圭子校長、小学生児童3人)は1903年創立の歴史ある学校です。今回の理科実験教室の講師は、関根幹夫先生です。日本蜘蛛(くも)学会の会員で、長く学校で理科を教えてきました。

9月4日の午前10時30分すぎ、関根先生は頭に「クモの巣」柄のバンダナを巻いたスタイルで、校舎の入り口にスタンバイ。すでに付近にいるクモの居場所をくまなく「調査」済みで、準備は万端です。児童3人が集まって教室はスタートしました。これまで経験したことがない「クモ」の授業に、みんな気持ちをワクワクさせているようでした。
まず関根先生は「スパイダーマンの関根です!」と頭のバンダナを指さしながら自己紹介。「クモは昆虫ではありませんよ!」から始まり、クモのオス・メスの見分け方や生態などをわかりやすく説明してくれました。
その後、学校の先生方も含めてみんなで近くの「クモの巣」を探し、ラッカースプレーや糊を使って巣の標本つくり、生きたクモを採取してそれぞれの名前調べなどに取り組みました。「このクモは飼育できますか?」と、クモの魅力に愛着がわき始めた児童もいました。
休憩後は教室に戻り、関根先生の「クモっていいやつなんだ」と題した話を聞きました。モニター画面でパワーポイントを使った説明を交え、関根先生が「世界には約5万2千種類、日本だけでも1700種類ほどのクモがいます。クモは昆虫を食べるために毒を持っていますが、人間がクモの邪魔をしない限り、襲ってくる心配はありません。稲から害虫を守ってくれる、守り神でもあるんですよ」と語りかけると、児童たちは熱心に耳を傾けていました。

最後に児童たちが「知らないことがわかって楽しかった!本当にありがとうございました」とお礼の言葉を伝え、実験教室を締めくくりました。